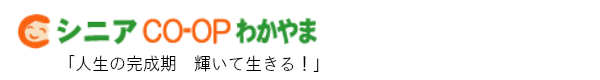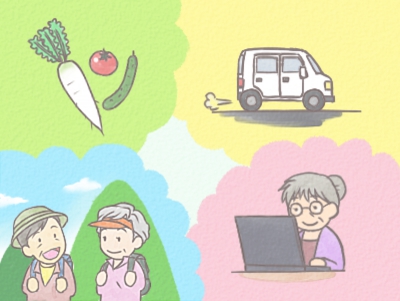赤穂藩士・高野の仇討ち第1話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第1話
明治四年(一八七一年)二月二十八日、紀州高野山麓かね河根宿の本陣中屋旅館に、武家風の一行が人目を避けるように二人、三人と分かれて入っていった。ぶっさき打裂羽織に袴の股立てを高く取って白の脚絆を巻いた旅装だった。
「備前藩の者である」と名乗った一行八人はそれぞれに表門から突き当たりの奥座敷に案内された。奥座敷から見える前栽には手入れの行き届いた松の木が趣をなしていたが、モミジなどの花木類は春先とはいえ、まだ枯枝や葉っぱのみとなっていて、どこか寂しい感がある。春、秋の盛りとなれば、さぞ見事であろうと思われる。
しかし一行には庭木を楽しむような心のゆとりがなかった。彼らは旅装を解くとすぐさま女中頭のお熊に言いつけ八畳二間、六畳二間の奥座敷の襖をことごとく取り除けさせ、さらに尾頭つきの肴を取り寄せるなどして四人の女中を相手に酒宴をはじめた。
八人のうち一人を除いて二十代から三十代に見え、旅館へ着いたころはどこか緊張感のただよった風であったが、酔いが廻るにつれて大声で歌いはじめる。そこへお熊が一同の気をほぐそうと三味線を弾きだすと侍たちの三人が立ち上がって踊りだす。興が深まり羽目が外れてくると、女中たちが片隅に大事そうに置いてある杉皮で包んだ五尺余りの細長い品物に興味を持ったのか、ふざけて踏もうとする。
「こらこら、それは高野山に納める大事な品であるぞ。踏んではもったいない」
一行の中の目鼻立ちの整った若い侍があわてて止めると、女たちはおもしろがって何度も踏む真似をする。
お熊は、このお品は何本かを束ねた短槍かも知れないと思ったが、そのころ十津川の郷士がこの宿場をよく通りかかり、槍を携えていたので気にも止めなかった。
ここ河根宿は高野街道の主たる宿場として栄えていた。高野参りの人々はその帰途、「精進あげ」として盛大な酒宴を開く風習があった。お熊らもそういった宴会は手馴れたものであったが、このお客さん方はどうして上るときにやるのか、といぶかりながらも接待を続けた。
一行は宴の合間に誰からともなく沈んだ様子を見せることもあったが、すぐにそれと気づくとまた騒ぎ出す。女たちに「杉皮の包みを踏むな」と注意した四郎と呼ばれる侍が最も意気盛んであった。
こうしてどこか不安感を引き払おうとするような酒宴が賑やかに夜明け前まで続いた。その間も誰かが訪ねてこないかしきりに気にしているようで、宴が仕舞うときに四郎が「もしわれらを訪ねてきた町人風の者があったら寝ていてもかまわぬからすぐ通すように」とお熊に頼んでおき、一同はやっと眠りに就いた。
備前藩と名乗った八人のうち池田農夫也(三十三歳)、村上四郎(三十歳)、行蔵(二十七歳)、六郎(二十五歳)は兄弟で、四郎、行蔵、六郎は赤穂藩士、農夫也は播磨新宮池田家の養子である。他の四人は村上兄弟の従兄の津田勉(三十九歳)、甥の水谷嘉三郎(二十歳)、そして六郎の剣友赤木俊三(二十九歳)、一番年配は赤木の叔父の大久兵助(六十歳)である。
村上兄弟とその助太刀の士は、高野山に逃れようとする仇敵を討つため先回りをしてこの宿に泊をとった。
今日まで剣術、槍術の師範に付き修練を重ねてきたが、命を落とすかも知れない。無事に本懐を果たしたとしても、どのような裁きが待っているかも知れない。彼らはそんな不安感を拭い去り英気を高めるため、宴を開いて羽目をはずしたのであった。
文久二年(一八六二年)師走九日夜、播州赤穂二万石藩主森忠典の詩会が開かれていた。
赤穂藩は元禄年間に浅野内匠頭長矩が江戸城内で吉良上野介義央に斬りつけた事件で、浅野家が取り潰しになったあと、永井氏を経て宝永三年(一七〇六年)森氏が入った。領知高は五万石から二万石に減じられていた。
森氏は源義家の子孫といわれ、可成の代で織田信長に仕えた。本能寺の変で信長とともに散った森蘭丸は可成の子である。その後、慶長八年(一六〇三年)に美作津山に十八万石を得るが、元禄十年(一六九七年)に除封。後に再興して赤穂へ入った。
藩主の近侍を勤める村上四郎が役目を終え、十二時前、帰り支度を整えているところへ四郎の甥である神吉長三郎という少年が息をはずませて駆けつけた。
「たった今、お父君が凶刃に倒れました。一刻も早くご帰宅ください」
「まことか、父上が凶変に遭われたとは・・・」
四郎は驚愕したが、それを面に出さず藩主忠典に報告する。
「それは大変なことじゃ。寸時も早く帰るがよかろう」
忠典も驚いて帰宅を促す。
四郎が家路へと急ぐすがら、ふと執政(家老)森主税のことが気になった。主税は参政(用人)である父真輔の上席で今夜の詩会にも出ており、四郎が凶変を聞く少し前に帰宅の途に着いていた。
父が不逞の徒の刃にかかったとすれば、ご家老も下城の途に襲われているのやも、との思いが迫ってくる。
「こちらへ知らせに来る途中、二の丸の外で異形の身支度をした十二、三人の者が白刃を提げて騒いでいるのを見かけました。恐ろしゅうございましたがそれを通り抜けてきました」
同行する長三郎が四郎の思いを察したのか、今しがた見てきたことを告げた。
「そうか。ご無事であればよいが」
心で祈りながらも二の丸を通りかかると、主税が襲われた直後らしく、通りには血にまみれた屍が横たわっていた。
「おのれ、卑怯なやつばらが」
四郎の若い血が煮えたぎったが、今ここで飛び出すと多勢に無勢、たちまち返り討ちとなろう。 あとに心は残ったが、からくもこらえて家路へと急ぐ。その途中、森家の門先を通ると門際に何か釘でも打つような音が響いてくる。不思議に思って近づいてみると三人の男が竹で矢来を結っている。
「閉門ではないか、なんと手廻しの早いことだ」
思いながらも四郎は長三郎を急かせ帰宅した。
四郎が帰ってみると母の阿従と弟の行蔵、六郎とほかに数人の親類の者が父の死骸を前に悲嘆にくれていた。阿従は夫真輔の遺体にすがりつかんばかりに泣き伏していた。 そうしているうちにも藩の検視役が村上宅に来た。
「検視に来るのが随分早いものだ。まるで下準備ができていたみたいだ」
四郎は不審に思ったが何も言えなかった。
医師を加えた検視役三名は、型どおりの検視を終えると、悔やみの言葉もなく引き上げて行った。
村上真輔には六人の男児と四人の女児がいた。長男なおち直内は京都在勤、二男駱之輔は河原家の養子で藩勘定奉行として大阪に在中である(三男以下は冒頭で紹介したとおり)。直内と駱之輔にはすぐ飛脚を立て通報した。
翌日になると村上一族すべてに閉門の申し渡しがあった。屋敷には森家同様青竹の矢来が結い廻された。
赤穂藩士・高野の仇討ち第2話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第2話
同じ夜の十時ごろ、参政村上真輔は赤穂城塩屋門外西の宅にあった。一帯は上仮屋と呼ばれ武家屋敷が居並んでいた。真輔はいま眠りに就こうとしていた。
そのとき、表玄関の戸をあわただしくたたく音が聞こえた。
「藩の御用でこれから京都へ参ります。ご子息様に何かご伝言はございませぬか」
家の者が急ぎ戸を開けると、西川升吉と名乗る三十前後の屈強な男が入ってきた。
ご子息というのは真輔の長男直内のことで、藩命を帯びて京都で周旋方を勤めていた。
「はて、この時刻に騒がしい。しかと確かめてみよう」
真輔は静かに起き上がり、次の間に出ようと襖を開け一歩踏み出そうとした瞬間、西川はいきなり土足のまま駆け上がり、腰の一刀を引き抜きざま真輔に斬りかかった。それを合図に、表に忍んでいた八木源左衛門、松本善次、山下鋭三郎、松村茂平の四人がそれぞれに白刃をひっさげて踊りこんだ。
「何をするか」
真輔は叫びながら必死で抵抗しようとするが、丸腰のうえ最初の一太刀による深傷でどうすることもできず、のめるように倒れた。そこへ四人が乗りかかって滅多斬りにし、息の根を止めてからその場を去っていった。
当時、赤穂では藩の主導権争いをめぐって、一方に公武合体派の森主税と藩の碩学村上真輔らの上級武士団があり、もう一方に尊皇攘夷を唱える西川升吉らを中心とする下級武士団が対立していた。
そのさなかに藩主の世子忠弘が世襲を待たずに十八歳で急死し、二男遊亀丸と三男扇松丸をめぐる継嗣問題が起こり、森主税らが遊亀丸を、西川らが扇松丸を推し、両派の対立に拍車をかけることになった。
文久二年正月、十六歳の遊亀丸が家督を継いで、藩主忠典となり、森主税が執政として藩政を任され、学問の師の村上真輔がその補佐である参政に就いた。
このことに不満を持った西川ら尊攘急進派は「君側の奸をのぞく」ことを名目として、森、村上を葬ったもので、後に「文久事件」と呼ばれ、その陰には、先年森主税らによって追い落とされた家老森続之丞が居たとされている。
(赤穂藩には家老職に四家があった)
森、村上を斬殺した西川升吉、八木源左衛門ら十三人は連署して藩の大目付宛斬奸状を出した。
それには「森主税は奸曲の者を近づけ御家を危急に、下民を苦しみにおとしいれた。村上は権威に募り奸曲にはたらいた。委細は口上にて申し上げる云々」と記されていた。しかしこの斬奸状は藩に取り上げられることはなく、森を襲った八人と村上を襲った五人は別行動で京都へ向かって脱出するしかなかった。西川ら下級武士集団はまだ門閥に取って代わる勢力ではなかったのである。
父が凶刃に倒れたとの報に接した村上家二男河原駱之輔は取り急ぎ京都の兄直内と連絡を取り、大阪を発しようとしたが「森家と村上家は閉門中、四面楚歌のありさま。いま兄弟が打ち揃って帰られては大層危険である。四、五日様子を見てからのことにするように」との、姉婿神吉良輔(長三郎の父)の言を受け入れ、いても立ってもおられぬ気持ちを抑えながら待機していた。
四日後の十六日、神吉から「今なら帰ってもよい」との密使が届いたので、船に乗り夕方赤穂浜の掛場に着いた。すぐ夕闇となりあたりを警戒しながら実家に着くと門口には青竹の矢来が厳重に結いまわしてあった。
駱之輔と直内は奇異に感じながら裏門から入ると、惣領と次兄の帰りを待ちかねていた母の阿従や弟の行蔵、六郎、親戚の神吉、津田などが出迎え、棺に納めてそのままにしてあった父の死骸の傍らへつれていった。
直内は寡黙で冷静沈着だったので、遺骸をみても悲しみに耐え膝に手をついたまま瞑目していたが、剛直な駱之輔は悲憤をこらえることができず、「無念だ」と一言発し、手を固く握ってしばし号泣した。
翌日、直内は藩庁に父の冤罪を訴えて、公正な裁断を求めたが、聞き入れられることがなかった。そればかりか、格禄を取り上げられ親類預けとなってしまった。
駱之輔のほうは十八日の早朝、大目付の呼び出しを受け「そのほうこと、家風に合わぬゆえ、永のお暇を申し付ける」との藩命が下された。
「何がゆえに家風に合わぬのでござるか。これまで藩のため、殿の御為に心身をささげてご奉公つかまつってきたのに。こたびのご措置は、それがしのみでなく一家の恥辱、一門の不名誉ではござらぬか」
駱之輔は言葉を尽くして反問を試みたが、大目付は「藩命である」と突っ張るのみであった。こうなると従わざるを得ず、妻と四人の子に別れを告げ、駱之輔は京都へと向かう。
駱之輔は六歳のときに請われて河原家へ養子に入った。文武に秀で藩主の覚えもよく、安政四年に藩校の教授方となり、さらにその年の初めに勘定奉行に取り立てられたばかりであった。
「永のお暇」という藩の仕置きに、駱之輔は耐えがたき思いを抑え、ともかく道を東へとり、寂しき足取りで歩んでいた。
「おーい、おーい」
後方から呼び声が聞こえてきた。うつろな心持で立ち止まって振り返ると、声の主が小走りで近づいて来る。それは妻の従兄八木権之助であった。
「何の御用ですか」
駱之輔が不審げに聞く。
「此度の藩の仕置きがあまりにも解せないので、八方手を尽くしてその後の動静を探ったところ、あやつらはまだ得心がいかぬらしく、駱之輔殿を狙っているようだ」
「えっ、何とおっしゃった」
「お主は兄弟の中でもとりわけ智謀のある偉丈夫、それだけに不気味な存在であろう。あやつらは京への道々に屈強の者を配置しておぬしを討ち果たそうと手筈を整えていると聞いた。ともかくも一度引き返されよ」
刺客である西川らは藩を脱出しているが、後にはまだ多くの同調者が残っていて、それらの者が村上家で最も才覚のある駱之輔の存在を恐れ、大勢の手だれを集めて襲おうとしているということである。
「それはよくお知らせくだされた。討ち手をさほど恐れるわけではないが、もし私が奸徒の手にかかって討ち果たされたならば当家の恥、この上は立ち帰っていさぎよく自刃をいたそう」
駱之輔は静かに踵を返した。
立ち返るといっても我が家へ戻るわけにはいかず、権之助と相談の上、村上家の菩提寺である城から北方の福泉寺に戻った。
すぐさま別れたばかりの妻子と親族を呼び集めた。後事を親戚一同に託したあと、「自刃する」と聞いて嘆き悲しむ妻女を説得する。
「そなたも武士の妻ならば、女々しき涙を見せてくれるな。父の死に殉ずるも孝の一つである。わしの覚悟は決まっている。権之助殿が知らせてくれねば、あやつらの凶刃に見苦しき最後をとげるところであった。幸いにして四人の男児がいる。後は託したぞ、しっかりいたせ」
さらに七歳の長男に向かって
「母上の言いつけをよく守り、大きくなって名を上げ、家を興すのじゃ。父の無念を忘れるでないぞ」と言い残すと、容儀を正して城に向かい瞑目、合掌した。
それを終えると傍らに座している舅に一礼する。
「不肖の婿をお許しください。いざ、ご介錯をお願い申し上げます」
さらばでござる、と絞り出すように最期の言葉を発すると、小刀をわき腹にぐさっと刺した。妻も子も目を覆って畳上に伏した。舅は万感の思いを捨て、大刀で頸を打ち落とした。
河原駱之輔、行年三十六歳。父真輔の変があってから九日目のことである。
閉門中の村上兄弟は誰一人駱之輔切腹の場に立ち会うこともできなかった。
赤穂藩士・高野の仇討ち第3話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第3話
文久事件のあと、その年の暮れも迫ったころ、森続之丞が執政となった。対立する森(主税)家、村上家はことごとく閉門中で、続之丞政権は安泰かと思われたが、その基盤は決して固いものではなかった。
赤穂藩は二万石の小藩で財政に余裕のないところへ、長年にわたって世継ぎ争いなど家中にごたごたが絶えず、そのうえ近年不作が続き年貢が思うように集まっていなかった。
三年前の安政六年、森主税、村上真輔が、藩主の不興を買って森続之丞が失脚したあと藩政の全権を握った。主税は家格によって家老職を勤めていたが、若年のため万事が華美で藩の窮乏にもあまり苦にせず、取り巻きを引きつれ酒食にふけるありさまで、江戸表への送金もままならぬ状態であった。
用人の真輔は主税の学問の師で年若い主税を補佐し、万事差配していたが、江戸表に出府していて書状を送って主税の所業を諌めていた。しかし一向に改める気配もない。やむなく赤穂に帰藩し藩財政の整理に着手した。真輔は、我が子であるが知恵者との評判が高く、藩主の覚えもよい駱之輔を勘定奉行に取り立て、塩税にてこ入れをしようと考えた。赤穂名産である塩業は、江戸時代の中ごろから商工業の発展に伴い、その利益は塩問屋を潤すばかりとなっていた。規制のゆるんだ塩業経営の改革を駱之輔に着手させ、塩税を上げることにより藩の財政を建て直そうとしたのである。その矢先に反対派によって追い詰められ自刃したのであった。
あとを受けた続之丞とその陣容には真輔と駱之輔のような才覚のある者はなく、疲弊にあえぐ藩財政のこれといった立て直し策も持ち合わせていなかった。
年が明けて早々の一月六日、村上の親類神吉良輔が大目付の呼び出しを受けた。
「十三人の者に対し、今後私怨は含まぬ、復讐もせぬ、という誓書を出すように」との申し渡しであった。
「村上一統はことごとく閉門を仰せつかり、かたや凶行を企てた者らが何らお構いなし。これだけでも一方的なご措置であるのに、ただいまのお言葉はあまりにも理不尽ではござりませぬか」
良輔は己れの立場が不利になるのも構わず抗議する。
「だまれ、身の程をわきまえよ。命に服さぬとあらばそちの家にも類がおよぶぞ」
大目付に従って同席している物頭が怒気をはらんで良輔を睨みつける。大目付が静かにそれを制す。
「これは内々の話であるが、土佐藩から十三人を無事に帰参させるようとの要請があったのじゃ。我が藩はこれを受け入れることにした。それでこたびのような運びとなった。いつまでも遺恨を持ち続けていれば、駱之輔のような不幸なできごとが起こらぬとも限らぬ」
諭すようで威しとも受け取れる大目付の言に、良輔は憤懣やるかたない思いであったが、「村上家の者と相談し、早々にご返事いたします」と答えざるを得なかった。
その場を辞した良輔は、さっそく村上家に出向き、親戚一同を集めると大目付から言い渡された藩命を伝えた。良輔が大目付に食い下がったように「ずいぶん一方的なご沙汰だ」「こんな藩命に従えば父上の御無念が果たせぬわ」という強硬な声が上がった。殊に四郎の怒りが激しかった。
「今ここで藩命に逆らえばどのような仕置きが来るかもしれぬ。そうなると永久にご無念を果たせなくなる。ここは忍び難きを耐え忍び、誓詞を出そうではないか。いざとなれば藩命を無視して決起する手もある」
最後は冷静な直内の意に従い、四郎も怒りをおさめ一同涙を飲んで誓詞を差し出すことにしたのである。
村上一族の誓書が藩庁宛に出された六日後に、隠居忠徳の名代として弟の森鉄之助が江戸表より帰藩した。忠徳は主税、真輔を信頼していて、鉄之助も村上贔屓であった。
城に入った鉄之助は家中一同の前で、藩主の代理として政事に携わっていくことを宣言した。藩主の縁戚でもあり、忠徳の命を受けているので、異議を唱える者はいない。続之丞は憮然たる面持ちで黙していた。
鉄之助は、ただちに文久事件の調査にかかった。
村上一族は事件以来ようやく公正な裁断を得られる機会が到来したと勇躍した。父の冤罪を訴え、二男駱之輔を死に至らしめた真相解明を求め、藩物頭に願い出た。二週間後、直内が閉門を解かれた。しかしこのとき直内は病に犯されていて、弟四郎の養家である須知家へ預かりとなった。母は実家の神吉家へ、妻も里方の脇坂家の家臣岡村方に引き取られた。
これでは亡父や駱之輔の冤罪が晴れたわけでもなく、わずかに閉門という恥辱をのがれただけのことで、村上一族は不満であったが、十三人の逃亡先である土佐藩の圧力に配慮した鉄之助の苦心の措置であった。
そんな折、西川升吉ら十三人が帰藩した。
事件のあと一時京都に逃れた彼らは、間もなく摂津住吉の土佐藩陣屋にかくまわれた。尊皇攘夷を標榜し、守旧派の執政および参政を切り捨てて脱藩したということで、彼らは土佐藩から優遇されていた。
土佐藩の実権を握っていた上士武市半平太(瑞山)からしばしば赤穂藩に対し、西川らの処分をどう決定したかと尋ねてきていた。武市は公武合体派の執政吉田東洋を暗殺して藩政を掌握した土佐勤皇党の領袖である。
十三人の肩を持つ森続之丞は次のような書状を送った。
「西川ら十三人が身命をなげうつ行動をとったことは評価するとしても、事件後領外へ退去し大藩である土佐藩にかくまわれたことは命を惜しむ所業である。(中略)彼らには、いったん入牢を申し付ける。(中略)彼らが自訴し入牢してしばらく静かにしていれば赦免する道がある。死を覚悟で自訴してきたものを我藩が命を奪うことはしない。以上のように自訴、入牢すれば貴藩も我藩も彼らも三方うまくおさまる」という内容であった。
この続之丞の意見が武市や中岡慎太郎らの同意を得て、十三人の帰藩が実現した。それは彼らにとって百日ぶりの帰郷で、土佐藩という大藩の後ろ盾があって、大手をふっての帰藩だった。
しかし彼らは鉄之助が藩主代行に就き、直内が閉門を許されたと知ると、執政森続之丞がしっかりと藩政を把握していないことに失望すると同時に自分たちが不利な立場に立たされたことを悟った。
不安を抱えたまま七日が過ぎたころ、藩庁から十三人に謹慎の申し渡しがあった。彼らは間もなく牢屋敷内に設けられた揚屋へ六箇所に分かれて入れられた。これらの措置は彼らが謹慎中にもかかわらず、土佐藩等への密書を出したのが露見されたからで、揚屋入りは鉄之助の指示であった。
揚屋へ入ってからも西川升吉が土佐藩宛に自分たちの窮状を訴える密書を出し、それを徒目付に押さえられたりしたので、鉄之助は十三人を本牢に入れた。
赤穂藩士・高野の仇討ち第4話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第4話
藩の目付衆が西川らの放つ密書を完全に押さえたつもりであったが、どこから漏れたのか土佐藩に届いたらしく、住吉陣屋から十三人の解放について、しばしば文面が届いた。藩庁ではそれを先延ばしにしていると、土佐及び長州藩から数名の使者が談判に赤穂へやってきた。
「正義人道のために奮起した者らをことさら重く処分するとは、何事であるか。この事態が長く続くのであれば当方も考えねばならん。あまりに偏った沙汰をなされては、貴藩のためによろしくあるまい」
大藩の傲岸な態度に、小藩といえども藩主代行の鉄之助は少しもひるまずに対した。
「先に当藩執政森続之丞からご返答申し上げたとおり、入牢してしばし静かにしておれば赦免いたすつもりでござる。西川らの処分は当方におまかせいただきたい」
使者らは赤穂なんぞの小藩が、いかほどのこともなかろうと侮っていたが、鉄之助の毅然とした態度にいささかたじろいだ。それでも大藩を笠に着た威圧が続く。
「西川の書面によれば、入牢以来監視が異常に厳しいとのことである。こちらは揚屋入り程度で、すぐにお構いなしと解しておった。約定に反しているのではないか」
「当方もそのつもりでござったが、謹慎中、あるいは揚屋入りの折に、他国への密書が露見するなど勝手な振る舞いが目にあまり、止むなく厳罰を命じた次第でござる」
一歩も譲らぬ鉄之助に使者は業を煮やしたが、こうして大仰に押しかけてきた手前、全く要求が容れられないとあっては面子にかかわると折れてきたので、結局双方を差し許す、ということで決着を見た。
その結果、森主税、河原駱之輔両家の名称復帰となり、村上家は五男行蔵の家名取り立てであったが、直内は病弱との理由で四郎(須知家)預けのままであった。
一方、放免された十三人には、赤穂藩への不逞浪人の侵入を取り締まるという名目で、海岸巡回の役目を与えられた。彼らは喜び勇んで新しい任務に就いた。
村上家の兄弟は、まだ父の冤罪が晴れたわけでもないのに、敵方が大手を振って街なかを闊歩する姿を苦々しい思いで見ていた。
「鉄之助様の苦しい心中を察し、よけいな騒動を起こすまい」と四郎は焦る心を抑えていた。
そんな四郎に病床の長兄直内が語りかけた。
「一味の者らは君命もないのに徒党を組んで、何の咎もない森家累代の臣を殺害した。にもかかわらず家臣として堂々と禄を食んでおる。どう考えても合点がゆかぬ」ここで直内は一息つき、気を落ち着けるようにしばし瞑目したあと静かに続ける。
「理不尽に殺された者の子孫は、復讐をなし得る資格を有している。藩は一味の者らに入牢させたかと思うと、任務を与えて自由に振舞わせている。本意がわからぬ。我らは今まで我慢を重ねてきた。この上は一時も早くことを運びたいと思うが、四郎の考えを聞きたい」
四郎は兄の淡々とした、それでいて決起を促しているような言に眼を輝かした。
「兄上の仰せのとおりです。当然我らには復讐する資格があります。いつまでも敵を横行させておくわけにはまいりません。やりましょう、ぜひ、ぜひ」
血気盛んな四郎がはやり立つ。
「では、このことを農夫也兄上に相談しましょう」
四郎は早速新宮の農夫也のもとへ文を出した。農夫也からすぐ返書が届いた。
「兄上と四郎がはやり立つ心情は察しますが、万が一失敗しては一味に糧を与えるようなもの。もう目の前に機会が来ているから、今しばらくのご辛抱を」
穏やかな諌めの手紙であった。これには農夫也の養家である池田家の意向もはたらいていた。農夫也に慎重な意見を出されてはどうにもならない。
直内と四郎の決起への思いはしばらく延期せざるを得なかった。
そのころ土佐藩では、藩政を握っていた武市半平太が藩主山内容堂によって退けられた。
容堂は幕政に関与し、中央で発言権を強めていったが、将軍継嗣問題で井伊直弼に敗れ、隠居謹慎に追いやられていた。桜田門外の変で井伊大老が斃れたあと容堂が復権し、藩論を公武合体に仕向けていった。同時に留守中武市が組織した土佐勤皇党を徹底して弾圧、壊滅に追い込んだ。これで武市が中心だった赤穂への干渉も一挙に途絶えることになる。
同じ時期、森鉄之助が藩主代行を辞職した。彼は文久事件の真相を調べ上げ、西川一味に相当の処分をする考えであったが、続之丞派の妨害があり、それを抑えると大藩の力を借りて圧力をかけてくる。それにも果敢に対抗していたが、疲れ果て嫌気をさして辞めてしまった。
このとき鉄之助は土佐藩の政変をまだ知らずにいた。
唯一のよりどころとしていた鉄之助の隠退に、村上兄弟は落胆した。
鉄之助が藩政の中枢から去り、執政続之丞の巻き返しが成り、西川らに有利に運ぶかに見えた。
ところが元治一年三月、西川升吉が再び脱藩し、以後七月にかけて事件に関係した十二人が、次々と脱藩した。彼らを支持する続之丞政権は決して安定したものではなかった。彼らのような軽輩には藩論だけが頼りであったが、その藩論自体があいまいである。
これより少し前、京都の政変が伝えられた。これまで朝廷で主導権を握っていた尊攘派の長州藩が、薩摩藩を中心とする公武合体派に取って代わられ、京都から追い出されてしまった。禁門の変である。この政変は尊皇攘夷を標榜する西川らにとって不安感をかきたてるものであった。藩も対処の仕方がわからず狼狽するばかり。人材なき小藩の悲しさである。
そんなとき村上家三男農夫也の養家である播磨新宮の池田家が兄弟の後ろ盾となり、その背後には岡山池田家という大藩が控えているとの情報が西川の元に届いた。村上兄弟の仇討ち決行に慎重だった池田家が、農夫也の懸命な説得にようやく支援を約束したのである。
西川は村上兄弟の復讐心に脅威を感じた。何といっても村上家は重代の名門で、そのうえ池田家が背後にいる。こちらは頼りにしていた続之丞はあてにならないし、今は土佐藩の庇護もない。
藩内の人々の反応も主税、真輔を殺害した当時は好意的であった。しかしあとを受けた続之丞政権が財政を好転させることができず、民衆の暮らしは困窮するばかりであった。彼らが帰藩以後「軽挙妄動、不逞の徒」「士魂なき軽輩の暴挙」と変わってきた。情勢の悪化に耐えかねた西川が先ず脱藩し、他の十二人がそれに続いた。
彼らは土佐藩を頼ることができず長州を目指した。
このことを知った直内と四郎は口惜しがった。血気にはやる四郎はなおさらであった。ぐずぐずしていると機会を失う。幸い農夫也の池田家が支援を約束してくれた。直内は行蔵と六郎も呼び寄せ、兄弟揃った中で以後の対策を考えることにした。
十三人が脱藩した直後、藩主忠典が病気を理由に突然引退し、かつて急進派が推した弟の扇松丸が十二代藩主忠儀となった。それでも彼らにはなんら好転をもたらさなかった。
赤穂藩士・高野の仇討ち第5話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第5話
長州藩を頼った十三人のうち奇兵隊に入隊できたのは八人であった。奇兵隊は高杉晋作が下級武士、農民、町人の有志を募って組織した非正規軍で、豪商らが支援していた。他藩からの脱藩者も入隊できたが、佐幕派の進入を防ぐため厳しく審査された。
十三人のうち西川升吉と最初から行動をともにしてきた兄邦治は入隊できたが、升吉ら五人が入隊することができなかった。土佐藩の待遇とは大きな差である。
五人が奇兵隊の選に漏れた原因は些細なことであった。赤穂藩の守旧派の重臣に天誅を加えたことで土佐藩へ脱出したときと同様彼らは誇らしげに長州へ入ったが、長州では、かつて赤穂に談判に赴いた藩士は奇兵隊にはかかわっておらず、審査役は彼らの「実績」には何の興味を示さなかった。それと気がつかない五人は入隊できるのが当然という態度であったため、審査役の不興をかったのであった。そのうえ、そのまま逗留していると佐幕派の疑いがかかる恐れがあると気づき、五人は急ぎ長州を去らなければならなかった。
明けて慶応一年(一八六五年)二月二十七日、西川升吉が彼の同志二人に赤穂福泉寺で殺害された。彼らは藩内の圧迫から逃れ長州へ落ち延びたものの、その地からも追いやられ、閉塞状態であった。こうなると西川に不満が集中してくる。そして焦燥から絶望へと移り、元凶である彼に刃が向けられた。殺害した二人はそのまま失跡した。
奇兵隊に入隊していた西川邦治は陣中で弟の死を知った。彼は弟を不憫に思った。一緒に入隊していればこんなことにはならなかった。升吉は幼いころから強情で向こう気が強かったが、頭の回転が早い利発な子だった。元服後はたびたび家を飛び出し、幕末動乱期の京都や西国諸国を巡っている間に尊皇攘夷論にふれ、次第に傾倒していった。
薩・長・土各藩の志士らとも交わるようになり、殊に土佐藩邸にはよく出入りしていたらしく、邦治はときどき家に帰る升吉から武市半平太の名を聞かされた。升吉は武市に気に入られ、敬服していたようである。
赤穂藩に尊王攘夷論が起こると、升吉は代表的人物として扱われ、文久事件でも首謀者と見られていた。
事件の夜、邦治は森主税を襲撃する組に加わったが、村上邸に向かった同志の話によると、升吉は真っ先に邸内に駆け込み、出てきた真輔に初太刀を浴びせたと言う。以来、升吉は急進派の花形となっていった。
藩論の優柔不断さと世評の変化から、彼らに対する評価が少しずつ変りはじめると、升吉は非難の矢面に立たされた。そして挙句の果てに同志に斬殺されてしまった。弟は自分の信じた道を歩んできた。執政として権力をほしいままにしていた森主税と、その黒幕とみなした村上真輔を斬ったのは、決して私怨や個人的感情からではなかった。すべて藩を思ってのことである。だのになぜこのような不幸な目に会わなければならないのか。邦治は弟を思い、悔し涙にくれた。
亡父真輔に初太刀を浴びせた西川升吉が、同志二人によって斬殺されたと聞いた村上兄弟は、一味十三人が脱藩したときよりも焦りを感じた。
升吉のほかにも森殺害組から二人、村上殺害組からも一人自害した者がいた。これでは亡父の怨みが晴らせぬまま敵が自滅していくではないか。
「今後私怨は含まぬ、復讐もせぬ」との誓書を藩庁に出していたため我慢を重ねてきた。その間、最も信頼する森鉄之助が藩主代行に据わり、一時的に村上方に有利に傾いたが、その鉄之助も藩政から退いてしまった。
村上兄弟はこれまで何回か対策を相談してきたが、仇敵全員が脱藩していまい、行方を捜す手立てもないままいたずらに時が経過していった。
慶応三年十月十四日、徳川十五代将軍慶喜が大政奉還し、十二月九日、王政復古令が発せられた。
続いて明治一年二月、明治政府より大赦が出され、赤穂藩もそれにならい村上直内は知行五十石となって再勤を許され、自刃した河原駱之輔の遺子には給人(藩士)末席を申し付けられた。
この大赦は加害者側にも及び、長州潜伏中の面々にも「家名取り立て、格禄も元のとおり」との沙汰があった。
四月には脱藩して長州に潜伏していた八人が、長州の使者に付き添われて新浜に着き、赤穂藩に引き渡された。奇兵隊に入隊した彼らは赤穂での鬱憤を晴らすかのように一兵士として懸命にはたらいた。
第一次、第二次長州征伐では幕府軍を相手にして果敢に戦った。しかし薩摩とともに政府軍となった長州にとって全国各地から集まってきた勤皇の徒は必要なくなってきた。赤穂脱藩組の戦績はどこにも記録されなかった。他国者の悲しさである。
この度の赤穂帰藩にしても大赦の名のもとに、体よく長州を追われたといえよう。それでも長州使者は「勤皇の志士としてよくはたらいてくれた。一同の将来のことはよろしく頼む」という意の言葉を残して行った。
八人はともかく安堵し、沙汰を待った。しかしすぐには城下に入れず、新浜村の正福寺に留め置かれた。
彼らの帰藩を待っていた村上方が、後ろ盾とする岡山藩を通じて、激しい仇討ち嘆願の運動を起こしたからである。岡山藩には村上家の娘婿である江見陽之進が大参事を勤めていて、これまで何回も申し入れをしている。
赤穂藩は藩内の意見の対立から結論を出すことができず、窮余の策として岡山藩に彼らの身柄を一時預かってもらうことになった。一行は六月に岡山に向け出発するが、その間一人が病死し、七人が岡山藩預かりとなった。
この窮余の策も長くは続かない。長州、岡山の大藩による干渉に赤穂藩は方針を決めかね、煮えきらぬ態度をとり続けたが、またも脱藩組一同を帰藩させ、それぞれの親族へ預ける措置をとった。
帰藩後、一同に永牢を申し付けられた、という噂が流れ、彼らの首領格が責を負って自刃した。これで村上家の仇敵は八木源左衛門、山下鋭三郎、田川運六、西川邦治、山本隆也、吉田宗平の六人となってしまった。
その二ヵ月後、今度は村上家長男直内が病没した。これは村上兄弟にとって大きな痛手であった。
「われらが本懐を遂げぬ間に兄上が身まかられた。無念のお気持ちが伝わってくる。われら不甲斐なきゆえこのような事態となった。兄上、お許しくだされ」
四郎は兄の亡骸にすがって慟哭した。
直内は病に伏せながらも常に病床から指示を出し、兄弟の支えとなってきた。その長兄が無念を晴らさぬまま黄泉へと旅立った。
四郎は兄弟の中で、父を襲った一味に対する敵愾心が一番強かった。その彼が最も激しく衝撃を受けている。これまで病床の直内に代わって指示どおり実行してきた。その兄が亡くなりどうしてよいかわからない。
やがて四郎の動揺が他の兄弟にも波及し、村上家の仇討ちも危うくなりかけてきた。
赤穂藩士・高野の仇討ち第6話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第6話
明けて明治四年一月十二日、赤穂藩は一味六人に対し、復籍を申し付けた。村上家にも直内の嫡子に七十石が与えられ、村上真輔には何ら罪もないと正式に言い渡された。これで念願の冤罪を晴らせたわけであるが、「今後遺恨を醸した方が曲事たるべし」という達しが付いていた。これには村上四兄弟は納得しかねた。いくら冤が晴れても、父の非業の死を忘れることができない。
「藩はなぜこのようなお達しを出すのか。もし法が義を害するときには、君子も法を犯さざるを得ず、と古語にある。曲事云々は藩が勝手に申し立てたこと。われらは義のために藩の命令を犯してでも、復讐の道をとることができる」
四郎が怒りを込めて言った。彼は今回の沙汰を聞くやいなや「今は動揺している場合ではない」と素早く立ち直った。他の兄弟もこぞって賛同する。
今回の沙汰が出たのと同じ日に赤穂藩は八木源左衛門ら六人に対し「紀州高野山の釈迦文院へ入って、森家代々の菩提を弔うよう」との藩命を下していた。
このとき行蔵が声をひそめて言った。
「仇敵六人が釈迦文院の我藩御廟所を守護するという名目で、高野山に送られることとなった。高野山に入れば仇は討てぬ」
ここで行蔵は真剣な眼差しで他の兄弟を見つめてから話しを続けた。
「藩のほうでも曲事云々という沙汰を出したが、それでも安心できぬのか高野山へ送ることにした。それゆえわれらはどうしても六人の者が高野の山に入るまでに目的を達せねばならぬ」
言ったあと行蔵は両拳を膝の上で強く握った。
このことは行蔵が言ったとおり、「遺恨を醸した方が曲事たるべし」、つまり怨みを持ったほうが悪い、との沙汰を出した藩庁が、それでも安心できなかったのと、長州、岡山両藩の圧力をかわす目的もあった。
これまで黙したままだった末弟の六郎が、今は長兄となった農夫也に訊ねた。
「こうなれば一日も早く決断せねばなりません。仇敵六人に対しわれらは四人、数においては劣っているが、われらには執念があり、悲願がかかっています。どういう手筈にて討ち取るか、まず兄上のご意見をお聞かせくだされ」
六郎は四郎に似ていてよくまちがわれる。容姿端麗で背丈が一番高く、剣術の稽古で鍛え上げた両の腕は節くれ立っている。彼は事件以来、江見陽之進宅に寄宿し、岡山藩の指南役を紹介してもらい、剣の修行に励んでいた。四郎と同様血気盛んである。
六郎の問いかけに、慎重な農夫也が答える。
「血気にはやって万一仕損じては恥の上塗り。ましてあの六人は実践の経験も豊富、油断してかかっては不覚をとる。幸い従兄の勉殿が助太刀を申し出てくれている。ほかにもう二人ほどほしいものだが。せめて森家に男児が一人でも居てくれたなら・・・」
農夫也が嘆くのは、森主税の遺児は女児ばかりであったからである。
四人がしばし腕を組みながら心当たりを思案する。
農夫也の言う従兄の勉とは、父真輔の妹の長男津田勉のことで農夫也よりも六歳上である。
勉は伯父真輔凶変の知らせが届いたとき、すぐさま槍を取り村上宅へ駆けつけたが、すでに刺客は去ったあとだった。それだけに強い義憤を抱き続けているという。
「何はさておいても岡山に相談してみよう。父上の冤が晴れたことも報告せねばなるまい。それに曲事云々についても義兄上のご意見もぜひお聞きしたい」
農夫也が出した意見に兄弟異存なく、その日の夕に行蔵が江見陽之進宅に向かった。
「長年の望みがかないこの上もなく喜ばしい。だが、曲事云々の沙汰はもってのほか。今は明治の世となったが幕府執政以来三百年、仇討ちを留め置いた例などは聞いたことがない」
江見陽之進は行蔵から舅である村上真輔の冤罪が晴れたとの報告を聞くと、心から喜んだが、「今後遺恨を醸した方が曲事たるべし」という藩の沙汰を聞くと、怒りを露わにした。
「藩の命令などを論ずる必要は毛頭ない。めでたく成功の暁は堂々と弁明もできる。少しも躊躇することはない、ただちに準備にかかるがよかろう」
陽之進にとって、岡山藩大参事の名で再三村上家の本懐について配慮するよう申し入れていたが、そのたび煮えきらぬ態度を見せつけられてきたのに、曲事たるべしとは、けしからぬという思いであった。
陽之進の後ろの席でつつましく聞いていた兄弟の姉であるお友が、父の雪冤の話になるとうれし涙にくれていたが、仇討ちにおよぶと、にわかに襟を正した。
「わたしが男であれば、おまえたちの手助けになって父上を殺めた仇敵の胸板に、怨みの刃を通してみようものを、女のこととて何の力にならず口惜しい次第。せめて神々さまにおまえたちの武運長久をお祈りします。立派に本望を遂げておくれ」
「姉上、ありがとうござる」
義兄の強い激励と、思いもよらぬ姉の言葉に行蔵は感激した。
続いて行蔵は助太刀のことと、仇敵を倒す手筈などを相談した。すると陽之進は厳しい表情をした。
「人だのみは愚かといえよう。少人数だからといって逡巡していては本望を遂げることはできぬ。断然四人でやるという覚悟を決めなさい。昔から仇討ちにおいて、寡をもって衆に勝った例はいくらでもある」
おっしゃるとおりだ、義兄の叱咤の言を聞いて、行蔵は恥ずかしい思いにかられた。
「行蔵、四人の力でしっかりやりなされ。相手の六人は奇兵隊で実戦の経験があるそうだが、こちらは四郎とお主は槍の修行に余念がないようであるし、六郎は我藩の指南役について剣を学んでいるが、進境は著しいと聞く。心してかかれば、よもや打ち損ずることはあるまい」
陽之進は行蔵の心内を察して激励の言葉も忘れなかった。
「あとのことは及ばずながらわしが引き受けた。心置きなく戦ってまいれ」
「ありがたきお言葉、兄たちにもお伝えいたします。仇敵どもはいつ出発するやも知れませんので、これにてお暇いたしますが、亡き父、亡き兄の仇は必ず討って見せまする」
岡山へ来てよかったと、行蔵は決意も新たにして帰途に着いた。
赤穂藩士・高野の仇討ち第7話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第7話
「喜べ行蔵、富田の嘉三郎が助太刀を申し出てくれた。 それにもう一人、赤木俊三殿といって六郎の剣友でな、 この御仁は六尺豊かで二刀流の達人と聞く。 こいつは心強いぞ。 願ってもないことだ」
江見宅で四人だけで決行しようと決意を固めて戻ってきた行蔵に、 農夫也が思わぬ朗報をもたらした。
嘉三郎とは新宮池田家の水谷某の妻である真輔の娘の三男である。 彼は富田家の養子となっていた。
嘉三郎は真輔が殺されたころはまだ幼少であったが、 長ずるにつれ祖父の事件の真相を知ると憤概がつのり、 ぜひとも実母に代わり仇討ちに加わりたいと申し出てきた。 これを聞き農夫也も四郎も手放しで喜んだ。
赤木俊三は岡山菅野村の出で、六郎と同じ岡山藩指南役の高弟、 剣を学ぶうち双方意気投合し、深い交わりを結んでいた。 剣の道は赤木の方が先輩だが、鷹揚な彼は対等に付き合った。 見るからに荒武者という風体で、農夫也が言うように願ってもない助太刀である。
四人の兄弟に三人の助太刀を得て、敵方六人よりも優勢となってきた。
嘉三郎は養家の富田家へ累をおよぼさないようにと離縁を申し出て、 実家の水谷姓を名乗ることにした。
仇敵一行は六人と田川運六の弟岩吉という十三歳の少年を供に加えて二月二十四日に赤穂を出発し、 坂越港より船に乗り、泉州堺に向かうとの情報が入った。
運六より十九もちがう異母弟の岩吉は幼いころから評判の腕白者で、 その将来に不安を抱いた田川家では、運六らに高野入りの藩命が下ったとき、 共に出家させようと同行を願い出た。 運六の同志五人は長い間苦楽をともにしてきた間柄なので快く受け入れ、 藩の許可も下りたことなので一緒に連れて行くことにしたのであった。
村上方は目立たぬよう二手に分け、農夫也、四郎、水谷嘉三郎、赤木俊三の四人が、 かねて用意をしておいた親類への遺書と藩知事(森忠儀)への届書を農夫也宅に置いて直ちに出発した。 もう一方の行蔵、六郎、津田勉の三人は赤木の叔父大久兵助を注進役として伴い、 同じ日に出発。加古川で双方が落ち合い、こちらは陸路を急いで先回りし、 高野山に入るまでに適当な場所を探し、仇敵を討ち取ることに決めた。
敵方より早く出発した村上一行は、加古川から兵庫を経て二十三日に大阪に入って一泊した。 翌二十四日は敵方が坂越港を船出する日である。
いつ着船するかも知れぬと、急ぎ堺の旅宿に入る。 そこでわずかな時間休憩をとったあと、兄弟が交代で海岸に出て見張りを続けるが、 一向に着船の気配がない。
「われわれの動きを察知して、にわかに行程を変更したのでは」
「いや、あれほど用心したのだ。感ずかれるはずがない」
いろいろ言い合っても見当がつかない。
「いいことを思い出した。浅五郎が確か堺の福地屋という酒屋に養子にきていた。 あの者に手を借りてはと思うのですが」
四郎が農夫也に相談する。
「浅五郎ならわしも存じている。 しっかりした男だ。 あの者なら信用できよう」
浅五郎は赤穂相生村の出で、父宗太郎は村上家の出入商人であった。 彼は侠気に富んだ若者だと兄弟は聞いていた。
農夫也の了解を得た四郎はさっそく福地屋を訪ねた。 父と兄の非業の死から仇討ちの決意にいたるまでの経過をつぶさに打ち明け、 助力を頼んだ。
「よくわかりました。 さぞご無念でございましょう。 私は町人ですからご加勢はできませぬが、幸い顔も知られていませんので、 敵方の動きを突き止め、逐一お知らせいたしましょう」
浅五郎は期待していたとおり快く引き受けた。
「七人という大勢の方が同じ宿にお泊りになっていては人目に立って、 どこから敵方に感づかれるかも知れません。 私の宅は広うございます。 明日からでも引っ越しておいでなさいまし」
浅五郎の親切な申し出に一同は感謝しながら福地屋へ移動する。
浅五郎宅に落ち着いた一行のうち農夫也、四郎、行蔵、勉、嘉三郎の五人は高野街道の道程を把握し、 仇討ちに適した場所を物色するため翌二十五日に堺を発った。
五人は河内長野を経て三日市、天見から紀見峠へとさしかかる。 ここは空海が高野山を開いてから京都、大阪方面と高野を結ぶ主要道路となる。 峠の北口には「高野山女人堂江六里」と刻んだ道標石が道端の草むらに抜きん出て建っていた。
六里石を過ぎ、峠のいただき付近にさしかかると比較的平坦な街道沿いに旅館や茶店が軒を並べていた。
ここは参詣人にとって南に高野の霊峰を望むには恰好の休み場であった。 しかし五人の一行にはそのような心のゆとりがなく先を急ぐ。 旅館街に連なった数十軒の集落を過ぎると峠道は下りとなり紀伊に入ると、 橋本の町と紀の川が見渡せる。
ひたすら道を急ぎ橋本宿で一泊し、 翌朝紀の川のあたりに出て橋本橋にさしかかった。 この橋は天正十五年に高野の高僧木食応其が架けたもので長さ百三十間あり、 高野へ参詣する人々の便宜をはかった。
橋の北詰一帯はそれまで雑草の生い茂る地であったが、 橋が架かるとともに次第に発展し、やがて橋本町と呼ばれるようになっていった。
「この橋を敵が渡ってきたところを、河原に降ろして勝負をかけてはどうであろうか」
気を逸っている四郎が四人に相談を持ちかけると、 慎重な農夫也があたりを見渡したのち、顎に手を当て思案する。
「橋の上なら挟み撃ちにできるが、通行の妨げとなろう。 河原に降ろせば逃がす恐れがある。 それにここは目立ちすぎるのう。 すぐに役人が飛んできそうだ」
「農夫也の言うとおりじゃ。わしもここでは無理だと思う」
年長の津田勉も農夫也に同調したので、四郎は仕方なく断念した。
赤穂藩士・高野の仇討ち第8話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第8話
農夫也ら村上方がやきもきしているころ仇敵一行は、情報どおり二十四日に坂越港を出て二十五日には飾磨に入った。そこから陸路を姫路へと向かい、三軒の旧知宅を訪ねて暇乞いをする。
「高野へ入れば多少の修行も持っていようが、ともかく平穏に暮らせるであろう」と心の通じ合った旧知からはなむけの言葉をもらい、暇を乞うたあとまた船に戻って一泊した。
二十六日は少し風が出て波が高かったので、そのまま出帆を見合わせ二十七日に順風に乗ってようやく堺に到着した。
翌二十八日早朝に堺を出発し、高野山へと急ぐのだが、入山すればそれぞれ所帯をせねばならぬので、土鍋や行平などを堺の町で買い揃え、背に負ったり棒でかついだりしながら分け持ちにした。
頭にはそろいの杉形の笠をかぶり、黒五つ紋の打裂羽織を着て荒い縦縞の袴という出で立ちである。
一方、農夫也一行五人が三日市の旅宿で夕食についていると、堺に残っていた六郎、赤木俊三、大久兵助の三人が駆けつけてきた。この宿の玄関には目印として三度笠を取り付けてあった。
六郎が勢い込んで言う。
「いよいよ仇敵を発見しました。二十六日には一行着船の様子がなく、二十七日にも同じように海岸に出て見張っていましたが、やはり姿が見えませぬ。困ったものだと思いながらいったん宿に戻りました。そこで私が何気なく二階の部屋の窓から見張っていると、その下を七人の者がぞろぞろ通るではありませんか」
農夫也らが「ほうー」と目を輝かす。
「私は喜び勇んで浅五郎に七人の風体をよく覚えさせました。浅五郎はすぐさま七人のあとを追っています。そのあとわれらは急ぎ兄上らを追ってきました。あの者らは明後日には入山するつもりでございましょう」
一同は、やっと敵の動きを捉えることができた、これは幸先がよいぞ、と口々に喜んだ。
翌二十八日には紀見峠に向かい、例の土橋の下に隠しておいた槍を取り出すと、津田勉が先頭に立って峠を越え、そして橋本、学文路を過ぎ河根宿の本陣中屋旅館に入ったのであった。
十四
中屋旅館で夜通し宴を開いて大騒ぎしたあと、夜明け前になってやっと眠りについた村上一行であったが、片時もせぬ間に女中頭お熊に起こされた。
「福地屋の浅五郎様がお見えになりましたので、お通しいたしました」
宴が仕舞うとき、四郎から「もしわれらを町人風の者が訪ねてきたら、寝ていてもかまわぬからすぐ通してくれ」と言われていたので、眠って間もなくで気の毒に思いながらも、聞いていたとおりの男が訪ねてきたので、そのまま彼らの部屋へ通したのである。
一行は飛び起きて身づくろいを整える。その間お熊は女中二人を呼び素早く寝具を片付けたあと出て行った。「昨夜から知らせを待っていた。仇敵の様子はどうだ。今どのあたりにいるか」
四郎が浅五郎に急がせる。
「はい、この宿を探すのに意外と手こずりました。何しろ旅館が多いもので、ここへきてやっと目印の三度笠を見つけたので急いで入って案内を乞いました」
浅五郎は安堵したように一息をつく。
「あの人たちは人目に立たぬよう三日市から紀見峠を越え、昨夜はここより手前の学文路宿へ泊りました。皆様方に追いついてしまう。気が気でなくお知らせにきました」
浅五郎は気もそぞろである。学文路といえば、ここ河根から一里(約四キロメートル)手前、河根峠を越せばすぐのところである。
村上一行はにわかにあわてだし、朝食もそこそこにすませると出立の用意にかかる。
浅五郎にはこれ以上かかわらせると万一の場合、類を養家に及ぼすことになりかねず、「今日はめでたく仇敵を討つ」との国許への文を託すことにして堺へ帰させた。
「さようなれば何分とも首尾よく果たされますように」浅五郎は仇討ちの成就を願いつつ、託された文を懐におさめて先に出発した。
一同が装束を整えると四郎がお熊にあわただしく言いつけた。
「笠はないか、深い笠があれば七つばかり用意してくれ」
急に言われても宿では用意できるはずがない。
仕方なくお熊が手ぬぐいを七本用意すると「やむを得ぬ、それでよいか」と七人が頬被りをする。
一同は供人の大久を金比羅参詣に仕立て、これに例の杉皮袋の槍を持たせ中屋旅館をあとにした。
「あのお方ら備前藩の者やと言うておられたけど、どうも変やなあ」
「あるいは十津川のおさむらいかも知れんなあ。どっちにしても元気なことじゃ」
中屋の女将や女中たちが小声でしゃべりながら後姿を見送った。
十五
春先とはいえ早朝の高野山麓は手も足も凍るほど冷たかった。村上一行は河根集落の南はずれの丹生川(紀の川支流で別名玉川)に架かった千石橋にさしかかった。この橋は寛永十一年(一六三四年)に幕府の命で作られた。以後七年ごろに橋の修理費として米千石が給せられたので、この名をつけられたという。別に、近隣の清水組千石の高野への年貢米がこの橋を渡って山上に運ばれたので、千石橋と呼ばれるようになったという説もある。
橋の手前右手には「高野山女人堂江二里」という道標石が立っていた。
千石橋を渡ると道は二分する。左手川沿いは粉撞峠を越えて奥の院裏に出る間道であり、右は高野街道の本道である。一行は右折して本道に入るといきなりその袂から険しい坂道である。そこをものともせず二町ばかり一気に上がった。彼らは後ろが気になって振り向きざま下方を見渡したが、丹生川の澄んだ流れと、朝霜の残った宿場の白い屋根瓦が目に入るだけで、仇敵らしい姿はまだ見えなかった。
赤穂藩士・高野の仇討ち第9話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第9話
なおも勾配の厳しい坂をひたすら急ぐ。朝早く出てきたので、まだ参詣人らしい者には出会わない。数町登るとそこに二十戸ぐらいの作水という村がある。いま登ってきた坂は作水坂と呼ばれていた。さらに数町登ると尾細という集落に出た。彼らはその道すがら仇討ちの場所を物色するが、思わしい所がない。
また数町登って少し視界が開けたところに出ると七、八戸ばかりの人家が道の右側に建っていた。桜茶屋という集落である。ここからの眺望がすばらしい。行く先には高野の山が巨大にそびえ、北を振り返ると河内、和泉両国と紀州の境である葛城和泉山脈が東西に走り、その麓を紀の川が豊かな水をたたえ、ゆっくりと西へ流れている。下界ではとても見られぬ光景であるが、一行はもちろんそんな景観を楽しんでいるような心のゆとりもなく、ただ仇敵の姿ばかりを気にしていた。
なおも十町ばかり登り、瘤のような小山の左側を通り過ぎると右手に観音堂があり、その赤い鳥居の脇を抜けると一町ぐらいのなだらかな道に出た。道幅は三間ほどである。左の方は松や杉の生い茂った山で、右の方は小松の生えた崖となっている。その向こうにかなり大きな一つの岩がある。地元では黒石と呼んでいる。この前後をさえぎってしまえばどこへも逃げることができない。
「これは格好の場所でござる。挟み撃ちにすれば逃がすこともない。ここに決めてはいかがかな」
四郎が急な坂を登ってきた疲れも忘れ、一同に問いかける。他の七人異存がない。
これ以上の適したところはない、と決戦の場所はすんなり決まった。
河根を出発して急坂を登りはじめたころから、小紋の羽織を着た四十過ぎを見られる男が後先になってついてくる。こちらの様子を探っているようにも見える。
「怪しいやつだ。まさか敵の回し者では」
血気の四郎が咎めようとする。
「そんなことはあるまい。ここで騒ぎを起こすとまずい。捨てておけ」
農夫也が止めた。そうしているうちにその<怪しい男>は先へと通り過ぎて行った。
ここを決闘の場所に決めると赤木俊三が共に連れてきた叔父の大久兵助を呼んだ。
「叔父上、長い道中ご苦労でした。最もよき場所が見つかったので、叔父上はこの下の瘤のような小山のうえに登って、仇どもが登って来たら、一、二町近づいたところで知らせてくだされ」
兵助は緊張の面持ちでうなずく。
「それから無事に成就したら一刻も早く国許に帰って、親類などに伝えてくだされ。それが叔父上のお役目、手出しはいっさいご無用でござる」
「心得た。俊三、いうまでもないが心してかかれよ」
兵助は直ちに小山へ向かった。この山は天誅組のお台場の跡である。
その間に他の者は崖から下の方に付いた小道に下りて例の杉皮包の槍を取り出し、それを使う四郎、行蔵、津田勉が手にした。
上の本街道では徐々に参詣の人通りが増えてきたが、彼らのこれからの行為を誰も知らずに通り過ぎて行く。
村上方七人は周到な陣立ての配備にとりかかる。まず津田勉が一番上段の黒石の陰に短槍を持ってひそみ、そこから少しはなれて反対側の小柴に四郎と行蔵が、これも短槍を持って身を伏せた。そこから半町(約五十メートル)ほどのところの道端には町人姿に変装した農夫也と六郎が腰を下ろした。農夫也は頬一面に膏薬を貼り、歯が痛んでたまらぬといった様子をし、六郎は従者としてそれを介抱しているといった演出である。さらに少し離れた小道を入ってすぐの窪みに水谷嘉三郎と赤木俊三が、農夫也と六郎の刀を持ってひそんだ。敵方が下から登ってきて一番近いところである。
「仇敵どもが二町ぐらいのところまで来ておるぞ」
瘤のような小山の中腹あたりで見張っていた大久が、いちばん近くにひそんでいる赤木に知らせてきた。そこからそれぞれの場所へ伝達していく。
「得たり」と一同に緊張感が走り、各人の武器である槍を手にし、刀に目金を湿して待ち構える。
前日まで二、三人連れで間隔を置きながら用心深く行動していた仇敵一行も、今日は高野が近づいてきたおで安心したのか、一団となって登ってきた。
先頭が西川邦治で、激しい坂を登ってきて、なだらかな道に出て安堵した様子で、その目には先兵としての警戒心もなく、一行は農夫也と六郎が姿をやつして座り込んでいる前を、気に止める風もなく通り過ぎた。
西川の次に吉田宗平、八木源左衛門、田川運六の三人が並んで歩く。少し遅れて山本隆也と山下鋭三郎が並び、いちばん後ろが運六の弟岩吉である。
西川が津田勉の隠れている黒石と赤木俊三がひそんだ窪地からの中間点に差し掛かった。
「今だ」
そのとき、赤木俊三がかねて打ち合わせたとおり叢の中から合図の空砲を二発放った。
相手方が不意の銃声に驚く瞬間の隙をねらい、それぞれ埋伏の場から飛び出して名乗りを上げ、一斉に斬りかかる作戦であった。ところがこのとき、にわかに突風が西から東へ吹きぬけたため、銃声は相手方の耳には届かなかった。
彼らは何事もなかったように先へと進み、先頭の西川邦治が津田勉のひそんでいる黒石まで近づいてきた。
手筈に一瞬の狂いが生じ、もはや一行の猶予もない。
「そこの仇敵ども、ようく聞け。われらはそのほうらの手にかかり、無念の最期を遂げた村上真輔のゆかりの者である。われは村上四郎なり、いざ尋常に勝負せよ」
まず四郎が飛び出し、槍を小脇にして大音声で名乗りを上げ、相手の機先を制した。行蔵がそれに続く。その大声がいちばん上手黒石の勉に届くとすぐさま飛び出し、勉も名乗りを上げる。下手の俊三と嘉三郎も叢の中から出て、農夫也と六郎に両刀を素早く渡した。彼らもつぎつぎと名乗りを上げ、それぞれに槍を小脇にかかえ、抜刀しながら敵に迫った。
赤穂藩士・高野の仇討ち第10話
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第10話
相手方は驚くのは当然である。これまで急坂をあえぎながら登ってきて、やっと平地に差し掛かり、荒野も近づき、やれやれと思った矢先の来襲である。一瞬の間に前後を完全にふさがれ、逃げ道はどこにもない。
戦闘は、まず勉が邦治の前途に立ちはだかり、槍を構えて突きにかかった。邦治も素早く太刀を抜いて応戦した。四郎と行蔵は闘いの流れの中で、八木源左衛門、吉田宗平、田川運六の三人を相手にすることになり、行蔵が後ろへ廻る間、四郎は三人を相手にすることになり、行蔵が槍で源左衛門の胸部を斜めに刺し、続いて四郎に刺されながらも立ち直って向かってくる宗平を刺した。
源左衛門は刺されながらも行蔵の額に一太刀あびせた。
「おのれ、小癪な」
行蔵もここで負けてはならじと短槍を握りなおし、源左衛門の腰のあたりを刺した。そのとき、運六が行蔵の後ろから耳のあたりを斬った。行蔵が逃れようと後ずさりをした隙をついて源左衛門、運六、山本隆也が四郎を取り囲んだ。苦戦となった四郎が大兵の運六に集中しているところを隆也が横合いから襲い、左耳上から左目にかけて切り裂いた。斬られた四郎は突然左目に火の玉が飛び込んだような激痛を感じ、一瞬眼前が真っ赤に燃えた。左手もしびれ、危うく槍を落としそうになった。
「もうだめか」
果敢な四郎も観念しかけたとき、六郎が山下鋭三郎の左肩に一太刀浴びせたあと、横っ飛びにかけつけ隆也の胴を払った。農夫也と俊三も加わり、刀と槍の穂先が鋭く交錯する中で、隆也と宗平が倒され、傷だらけになりながらもしぶとく闘った源左衛門も止めを刺された。
いちばん若年の水谷嘉三郎は、竜野藩の剣術師範に師事し、目録の腕前であったが、実戦は初体験で相手の刀先だけが目に入って、隙はおろか敵の動きさえもとらえることができなかった。道場と実戦のちがいを、身を持って知らされた。それでも闘いが進むにつれて相手の動きも見え、道場で修練を積んだ技も発揮できるようになってきた。こうなってくると村上方には強い戦力となる。兄弟の中では比較的剣の腕が劣る農夫也に付き、最後まで助勢し守った。
最初に先頭を行く邦治に一槍入れた勉は、そのまま渡り合っていたが、不覚にも木の根に足を取られて転倒した。得たり、と打ち下ろす邦治の一刀に深手を負ったが、ひるまず組打ちとなり激しくもみ合った。これに気づいた農夫也が駆けつけ右肩から袈裟懸けに斬りつけると続いて嘉三郎が胸を突き刺して邦治を仕留めた。
敵側の中で最も強敵といえる運六は最後まで凄惨な死闘を展開した。彼は不意を襲われたため、荷を背にしたまま闘った。全身数ヶ所に傷を負い、血だるまになりながらも激しい抵抗を続けた。味方の中で最も腕が立ち、運六に見劣りしない風格の俊三が出て、一騎打ちとなった。同じ条件のもとであれば、伯仲の勝負が展開されたであろうが、このとき運六は相当弱っていた。彼は最後の力を振り絞って二刀流で構える俊三に斬りつけた。俊三は両刀でがっちりと受け止め、はじき返すと同時に大刀で肩先を斬った。運六はたまらず仰向けに倒れた。
「今だ、四郎殿、止めを」 俊三はあとを四郎に譲る。四郎は片目がつぶれ左腕もきかない重傷の身で、脇差を右手に息絶え絶えの運六に馬乗りとなって止めを刺した。若い嘉三郎はすさまじい怨念と闘魂をむき出しにした叔父の姿を瞬きもせず見つめていた。
この闘いの中で哀れをとどめたのは田川岩吉である。村上方ではこの少年の同行を知ったときから、手を加えないことを申し合わせていた。
「おまえは関係ないから、早く立ち去れ」
嘉三郎は刃向かってくる岩吉を何度も諭した。
「私でも武士の子、逃げはせぬ」となおも向かってくる。田川家は身分が低く、三人扶持であった。それゆえ兄運六はそこから脱皮しようと西川升吉らの誘いに応じて文久事件に加わった。
一時は「自分たちの時代が近づいた」と単純に喜んだこともあったが、事件後は総じて苦難の連続であった。岩吉は自分を慈しんでくれる兄を慕っていた。この度の高野への道中でも自分を同行させていることに気を使い、ずっと大きな荷を背負って歩いた。そして不意打ちを喰らったのでそのまま戦わざるを得なかった。その兄の壮絶な最期を目の当たりにしている。どうして自分一人がこの場を去れようか。
自分を逃そうとする少し年上の若侍に、初めのうちは好感を持っていた。しかし兄を死なせた相手方の一人だと気づくと、にわかに少年の胸中に怒りが湧いてきた。
相手は父あるいは一族の柱を討たれ、苦難の道を歩んできたかも知れない。しかし、それでも藩の名門に属する家柄である。こちらはその日の生活にも事欠く下級武士だ。そんな反発も起こってきた。
岩吉は「兄のかたき」と心中で叫び、両手で刀を振り上げ嘉三郎に向かっていった。
驚いたのは嘉三郎である。ほんのかすり傷でも追わせて追い払うつもりであったのに、すさまじい勢いで追ってくる。相手の勢いをかわし、肩先に軽く一太刀浴びせるつもりが、手元に思わぬ力が入って、岩吉の後頭部から襟元にかけて刃が深く入ってしまった。
十七
死闘は半時(一時間)あまりで終わりを告げた。もはや立ち向かう者は一人も居なかった。
村上兄弟はここに仇敵六人を討ち果たし、念願を成就した。
「まずは重畳」
一同は血のにじんだ手槍や刀を提げたまま顔を見合わせて安堵した。七名とも着物はずたずたに切り裂かれ、刀はみな鋸の歯のようになっていた。不意打ちとはいえ実戦の経験を持つ六人もの強敵を討ち果たし、互いに健闘をたたえあった。それから俊三と嘉三郎が用意の白布を取り出し、傷を負った四郎の顔面を包んだ。
一同の中で四郎がいちばんの深傷で、面部のほかに肩先と手の裏にそれぞれ一ヶ所の傷があった。勉が顔と手に深傷、六郎が右の手の甲に長い傷、農夫也が足から手にかけていたるところに浅い擦傷、行蔵は額と耳に軽傷、俊三と嘉三郎は無傷であった。
赤穂藩士・高野の仇討ち第11話 NEW
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第11話
四郎、六郎、勉は傷の応急措置を終えると、しばらく叢の上で仰臥して休息した。他の四人は死骸をひとつひとつ改めた。すると死骸は五体しかない。山下鋭三郎の姿が見えないのである。一人でも逃がすことはできない。
「しまった、逃がしたか」
一同は眼前の敵と戦うのに精一杯で、山下が逃げるのには気がつかなかった。あわてて探しはじめると
「山下なら私が一撃あびせた。確かな手ごたえがあったから遠くへは逃げられないはずです」
六郎が胸を張って言う。手分けして付近を探すと、脇道を一町ほど入った窪みにうつ伏せで倒れているのを発見した。まだ息があったので、行蔵が止めを刺した。
負傷者の応急手当をすませると、真輔、直内、駱之輔の戒名を書き記した紙を路傍の松の木に貼り、その前に六人の首級を供えて仇討ち成就を報告した。
「ご立派なことでござる。命がけで戦っているあなた方よりも、じっと見ている私の方が恐かった。それではこれから国許に立ち帰り、ご一統にお知らせいたします」瘤の小山で一部始終を見守っていた兵助が駆けつけ、言い終わると同時に急坂を下った。
「かたき討ちじゃー、赤穂武士のかたき討ちじゃー」
道すがら兵助は喜びを抑えることができず、大声でわめきながら走っていった。
すべてが終わり、農夫也と行蔵が自首して検視を受けるため五条に向かった。当時高野は五条県の管轄で、後に和歌山県へ、五条は
奈良県に編入される。
二人は河根に下り、中屋旅館に戻ったのは午後二時すぎであった。
初めて応対に出たお熊は、髷が乱れ着物が擦り切れた二人の姿を見て仰天し、女将のもとへ逃げ込んだ。
お熊は先ほど上の方から下りてきた村人から「神谷の黒石でえらい喧嘩があったんや。立派なさむらいが七人も殺されたそうやで」と聞かされていた。その相手が昨夜どんちゃん騒ぎをして、今朝送り出した八人のおさむらいだとは思ってもいなかった。
「何ごとや、落ち着きなさい」
女将のお近はさすがに肝が据わっている。お熊をたしなめ、ゆっくりと出てきて農夫也に事情を聞いた。
「前夜はたいそう世話をかけた。われらは備前藩の者と申していたが、実は藩州赤穂の藩士である。只今親の仇敵六人を黒石において無事討ち果たした。これから五条県に自訴して出る。たった一夜の泊りであったが多少の縁、まあ喜んでくれるがよい」
農夫也がていないに一部始終を話すと、女将のお近はいたく感動した。
「さようでございましたか。それはどうもおめでとうございます。昨夜からのご様子がおかしいと今朝からもお噂をしていたところでございます。何はともあれお祝いにお酒など召し上がってくださいませ」
二人はすすめられるまま上がり口に腰かけ、用意された杯をとった。ゆっくり味合う間もなく駕籠を呼んでもらう。
「何をびくびくしとんのや。このお方らは立派に親の仇を討った赤穂のおさむらいさんやで。早う出しなはれ」お近は後難を恐れて尻込みする駕籠屋を叱り飛ばして、二挺の駕籠を五条まで送り出した。
十八
農夫也、行蔵が五条に向かったあと、仇討ち現場に西郷村の庄屋が来た。決闘最中の現場を通りかかった村人が肝を冷やして通報してきたからである。
「当村は五条県のご支配で、私が庄屋を勤めています。委細をお話し願います」
庄屋は慇懃に尋ねた。松の木の根に六個の首級が並べられ、ところどころに首なしの死体が転がっていた。
四郎は仰向けに倒れ、勉はつくもり、六郎は立っていて、俊三と嘉三郎が四郎の傷を手当していた。
勉が静かに立って言った。
「われらは播州赤穂の者で、乱暴狼藉をはたらいたのではない。九年前に父を討たれ、その仇を只今無事に討ち果たしたのである。決してご心配におよぶものではない。しかし、村方を騒がしたことは重々恐れ入る」
「さようなれば、ともかく姓名をお聞かせください」
これを聞いて嘉三郎が矢立を取り出し、姓名を記して庄屋に渡した。
「五条県へのお届はまだですかな」
「われらのうち二人が先ほど届けに参った。それよりもお見かけのとおり深手を負った者がおる。お手数ながら早々にお世話を願いたい」
勉がていねいに頼むが、庄屋は少し渋る。
「御検視がすんでないので、いたしかぬますが」
「それもよくわかるが、この者の深傷は捨ててはおけぬ。御検視にはわれらが必ず申し開きをし、庄屋殿にはいささかのめいわくもかけぬゆえ、何卒よろしく頼む」
百姓に対して深々と頭を下げる勉の姿に、庄屋も断りきれない。とりあえず深手を負った四郎を戸板に乗せ村方へと送る。
「庄屋殿、こちらへ来てくだされ」
嘉三郎が庄屋を死骸の転がっている端で苦しんでいる岩吉のところへ連れて行く。
「おう、まだ子どもやないか」
驚いた庄屋は岩吉の耳元へ口を寄せる。
「おまえさんの傷は浅いから助かるぞ。御検視がすんだら医者に診てもらうようにするから、気を確かに持つんやで」
岩吉は何か言いたそうであるが、声が出ない。庄屋が水を与えると、口から入った水が襟元の傷口から赤くなってら流れ出た。少年は間もなく息を引き取った。
「すまぬ、私の腕が未熟なばかりに・・・」と嘉三郎が瞑目して合掌した。
「かわいそうに、まだ年端の行かぬ身で」
庄屋が思わず落涙した。
十九
検視が来るまで庄屋は続々と見物に集まってくる村人のうち、これはと思う五、六人に指示し、討たれた者らの大小の刀七振りと所帯道具などを一つにまとめ、盗難されないように番をさせた。さらに死体一体ごとに三人ずつ付けて検視までの見張りをさせた。
赤穂藩士・高野の仇討ち第12話(最終) NEW
2020-05-07
赤穂藩士・高野の仇討ち第12話
そうしているうちに午後八時となり、五条県から検視の役人が医者二人を連れ、傷を負った四郎ら五人が保護されている旅宿大家孫兵衛方に到着した。
農夫也と行蔵の自首を受けた県庁では事の重大さに驚きつつも、とりあえず検視役と医師の三人を急行させた。まず庄屋が「決闘」の概略を報告し、黒石の現場へ返した。その間に四郎の傷を見た医者が、「生命の保障なし」と首を横に降った。
表座敷に入った検視役は尋問をはじめる。初めに怪我人に配慮して嘉三郎が応じたが、若年ゆえ詳しい経過がわからぬこともあり、検視役は勉、六郎らが休息している一間まで尋ねた。彼らは検視役に文久事件にはじまる一切を申し述べた。庄屋があらましを報告してあったので、尋問はそう時間を取らなかった。
尋問を終わったあと、検視役は一同の大小五腰と槍三筋をまとめ、大家方の土蔵へ厳重に保管しておくよう命じて引き上げた。
その日の午後から降り出した雨は、夜に入って雷鳴を伴う強い風雨となった。村人は死骸をひとまとめにして番小屋の中へ運んだ。この雨は死骸の管理には難儀をしたが、決闘のあった場所には清めの雨となった。
真夜中過ぎに五条県の上席役人が先刻の医者二人を連れて大家方に着いた。医者が死骸の検分を終えると、俊三と嘉三郎を連れて五条に引き上げた。
四郎、六郎、勉の三人は疵養生のため、しばらく大家方に逗留することになった。
「ほとけを埋葬するように」と上席検視役が命令していったので、下役人の指示で急に七つの棺桶をつくり、死体と首を合わすのに一苦労だったが、ようやく手伝いに借り出されていた村人一同は埋葬を終えた。
四郎ら手負いの三人には五条県から、一人一人に看病人を付けておくようにとのことだったので、庄屋は村の女三人を雇ってつけるようにした。
命の保障はない、と医者からいわれていた四郎であったが、日に日に回復していった。無事本懐を果たしたからであろう。
彼は兄弟の中で最も浅野家の赤穂浪士に影響されていた。赤穂の士族であるだけに、親の仇を討たぬは恥であり不孝であるとの観念に取り付かれていた。それだけに父の憤死から九年間も心に重くのしかかっていた「仇討ち」という偉業を成し遂げた充実感から、生命力が湧いてきたのであろう。
十日間で回復した四郎は、三月十日に六郎、勉と五条県へ引き渡され、先に自訴して留め置かれていた農夫也、行蔵、そして次に送られた俊三、嘉三郎とともに五条町の牢に入れられた。
二十
牢に入った村上兄弟ら七人は、二十日ののち旅宿常楽屋善兵衛方に預けられることになった。
五条県では七人を事情聴取した上で、政府に具申書を提出し、その指図を待つこととなった。
この聴取の中で、仇敵との決戦の直前に村上一行を付け回していた<怪しい男>の正体が判明した。その男は五条の目明しで、一行の挙動に不審を抱き、すぐ先の神谷宿に着いたら手配しようと通りすぎたのであった。「危ないところであった」と彼らは胸をなでおろした。五条県は七人に対して「親の仇を討った村上兄弟」として寛大な扱いをした。常楽屋預かりもそのひとつで旅宿では丁重にもてなした。そんな待遇が一年間も続くが、その間の明治四年(一八七一年)十一月二十二日、五条県が廃止となり、事件の起きた高野山(伊都郡)は和歌山県の所管となり、七人は翌明治五年三月、和歌山に移された。彼らは五条から川舟に乗り、紀の川を下って和歌山の城下に着いた。
和歌山県でも五条県に彼らの取り扱いを問い合わせたりして、丁重な待遇をした。全員揚屋へ入ったが、戸締りもなく互いの行き来は自由であった。
だが、ここでの生活は三ヶ月で、同年六月には大阪へ移されることになり、一ヶ月前に新しく開設された大阪中ノ島の司法省臨時裁判所で裁判を受けることになった。ここでは五条、和歌山とちがって松屋町の獄舎に投ぜられ、七人はかわるがわる臨時裁判所に呼び出され、大判事から取調べを受けた。
司法省部内では、厳正に処罰すべきであるという意見と、無罪にすべきであるという意見にわかれていた。
前者は、文久事件については大赦をもって双方無罪となり「今後私怨は含まぬ、復讐もせぬ」という誓書まで出して解決している。ゆえに今回の件は「仇討ち」とは認めがたい主張する。
これに対して後者は、旧来の仇討ちを義務とする風習を重視し、無罪とすべきであるという考え方である。
大阪臨時裁判所が出した判決は全員死刑であった。
「赤穂義士と同じか」と一同は衝撃を受けた。彼らは五条、和歌山で破格の待遇を受け楽観していた。
村上四兄弟はすぐに覚悟を決めたが、助太刀の三人のうち、血のつながっていない赤木俊三には、気の毒な思いでいっぱいだった。
「気にされるでない。もともとその覚悟でござる」
男気の俊三は豪快に言い放つ。
この判決も仇討ちの直後から続けられた助命減刑運動が効いたのか、翌年二月には次のように減刑された。
池田農夫也、村上四郎、村上行蔵、津田勉 禁固十年
村上六郎、水谷嘉三郎、赤木俊三 准流十年
准流とは流刑に変わる一時的な刑罰で、各府県の監獄で服役した。
さらにその後、罰金を払うなどして、明治九年までには全員自由の身となった。
明治六年二月七日、太政官から「仇討ち禁止令」が出された。高野の仇討ちが法整備を促したことになった。村上事件が、日本最後の仇討ちといわれているが、禁止令公布後も何件かの仇討ちが発生している。したがって村上兄弟によるこの事件は、美徳とされた封建時代の合法的な最後の仇討ちといえよう。
二十一
決闘があった現場から四町ほど登った神谷の入り口に、討たれた七士の墓地がある。七人の遺体はここに埋葬された。墓碑は田川兄弟で一基、他はそれぞれ一基ずつ、ほぼ同じ型で六基、道から少し入ったところに並んでいる。
封建武士道最後の意地を貫き通すことができた村上兄弟にくらべ、時代が自分たちに有利に流れているのに、それにも乗ることができず、高野山へ逃れる目前に散った彼らも無念であったろう。
六基の墓碑の戒名にはすべて「忠」の字が刻まれていた。
終わり