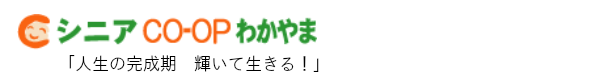引き潮の如く第1話
2020-05-07
引き潮の如く第1話
天正九年九月のある日、織田信長の三男、三七郎信孝は父から火急の呼び出しを受けた。
「三七、そちらに紀州高野山攻めの総大将を命ずる。一万の軍勢を預け、副将として久太郎をつける。見事ふらちな坊主どもを成敗して参れ」
一瞬信孝はとまどいを隠し得なかった。思いも寄らぬ父の命令である。信長は我が子のかいま見せたその表情を見逃さなかった。
「なんじゃ、そのほう不服があるともうすか」
父の射すくめるような眼光に、信孝は縮みあがらんばかりである。
「滅相もござりませぬ。ありがたき幸せ、つつしんでおうけいたしまする」
信孝は平伏して座敷を退いた。
「父上はむごい、なぜ信雄ではなくなぜ自分に」
信孝は気が重かった。彼はこれまでの父の仏門攻撃には、口には絶対に出せないが快く思っていなかった。
信長は十年前の元亀二年九月、比叡山を焼き討ちにした。根本中堂、三王二十一社をはじめ、霊仏、霊社、僧坊、女、小童の区別なく数千の頸を打ち落とした。死体があたりかまわずころがっていたという。
その前年、越前の浅井の兵が叡山に立て籠もったとき、信長は山門の衆徒に「中立を保つよう」鄭重に要請した。が、彼らは宗門の権威を背にしてこれを拒み浅井、朝倉に荷担して一時信長を苦しめた。その報復としての焼き討ちである。
衆徒らはいくら猛将信長といえども、よもや神仏にまでは手を出せまい、と高をくくっていたのである。
「おなごどもが泣き叫んで命を乞うても、お館様はお許しにはならなかってのう。戦場とはいささか違うた光景でござった」
信孝は叡山襲撃の一部始終を、織田家重臣のうち最も信頼のおける惟任日向守光秀から安土城の一間で聞いた。
このとき信孝はまだ十三歳であった。
天下をとらんとする武門に生を受けたとはいえ、狂気といえる父の行為に感受性の強い若き心を悩ませていた。
光秀の語り口は性格明快で、焼き討ちの状況はありのまま漏らさず話していると信孝は解しているが、心中は批判的であろう、いや絶対にそうであってほしいと強く望んでいた。
信長の仏門攻撃は叡山のみにとどまらない。長年の敵であった、伊勢長島の一向一揆を天正二年九月に討伐したのであるが、その際積年の憎しみから中江、屋長島両城に籠城している男女二万人を、幾重にも柵を設けて閉じこめておき、四方から火を放ち焼き殺したのである。
「いくら憎くとも酷すぎる」とこのとき信孝は一揆勢に対するあわれみよりも虐殺を繰り返す父に戦慄を覚えた。
信孝には、二人の兄がいる。二歳上の嫡男信忠と同い年の信雄で、二人は事実上の正室である吉野(尾張の名門生駒氏の息女)の子であるが、信孝は異腹である。
信忠はこのときすでに安土城へ移った信長から岐阜城と尾張、美濃の二国を譲られており、総領としての地位を固めていた。信雄は軽率なところがあり、父の信頼を得ていなかった。
引き潮の如く第2話
2020-05-07
引き潮の如く第2話
昨天正七年九月信雄は父の下命に従わず勝手に伊賀の国へ兵を出し、武将の何人かを討ち死にさせた。激怒した信長からは〈勝手に伊賀に兵を出すなどということは、あってはならない。・・・大事な武将たちを討ち死にさせたことは言語道断、けしからぬことである。そなたがそのような心がけでいるのでは、親子の縁も認めるわけにいかない〉という内容の厳しい書状を送られたことがあった。
「父上の命に従わず勝手に兵を動かすとは。こんな恐ろしいことを」と信孝は信雄の行動が理解できなかった。 こんな信雄であるのに、身分の低い側室の子である信孝には常に見下した態度をとっていたのである。
信孝はその慎重な性格ゆえ時に行動が遅れ、短気な父から「ノロ」と呼ばれていた。
かつて摂津に出陣した際もわずかに敵への攻撃を逡巡した。幸い味方は大事に至らず信長も何もいわなかったが、信雄が「ノロ殿の面目躍如なり」と揶揄したのである。
「何で信雄ごときに侮りを受けるのか」と地団駄踏む思いを抱いたこともあった。
父の一連の仏門攻撃に対しても信雄は何の疑問も抱いていないばかりか、同じ行動に出るやも知れない。
父が近いうち高野攻めの裁可を降すであろうことは信孝にも予測できた。しかしその役目は当然信雄だと思いこんでいた。
「何故自分に・・・」と信孝は暗澹たる思いであった。
信孝が明智光秀と初めて遭ったのは十歳の折、永禄十一年九月信長が足利義昭を奉じて上洛したときである。
翌十月義昭は室町幕府十五代将軍となるのであるが、光秀は細川藤孝とともに義昭擁立に大きな役目を果たす。彼は室町幕府滅亡後、信長の天下平定戦に参加し重用されていく。
そのころまだ幼かった信孝ではあったが、教養豊かで理性的、そのうえ武人としても城攻めなどですぐれた戦略を持ち、父とは対照的な兵家である光秀に次第に魅かれていった。
「三七さまは大将としての器量を裡に秘められておられる。もっと自信をお持ちなされ」
光秀はことあるごとに信孝を励ました。
「お館さまは、ノロとお呼びになさるが、三七さまに期待をかけておるからでござるよ」
他の重臣らは主君からあまり信を得ていない次男と三男をどことなく軽んじていた。
殊に光秀と並ぶもう一人の実力者羽柴筑前守秀吉などは露骨に嫡男信忠にすり寄り、信孝には態度にこそ出さないが無視する姿勢が窺えた。
秀吉は戦勝報告などいち早く信長のもとへ走り、次に信忠へと行くが、信孝には知らぬ顔であった。
「要領居士の筑前ザル奴、うぬは惟任の足下にも及ばぬわ」
信孝は腹中苦々しい思いであったが、秀吉に劣らない光秀に認められていることが何よりの救いであった。
高野攻めの命が降ったその翌月、総大将織田信孝が副将堀久太郎秀政と一万の軍勢を従え、紀州伊都郡加勢田(笠田)の背の山へ本陣を構えた。
この地は真北に和泉山脈が走り、南に高野山を望み、その麓をゆったりと流れる紀ノ川を見下ろす小山で、要害に適していた。
「妹に恋ひ わが越え行けば 背の山の 妹に恋ひずてあるが羨しさ」(作者不詳)と河南の妹山とともに万葉集に十四首も詠まれている風光明媚な地でもある。
織田方と高野方の紛争の発端は、前年の天正八年三月に荒木村重の旧家臣をかくまったことにあった。
村重は摂津の伊丹を居城として信長に従っていたが、天正六年十一月突然謀反を起こした。しかし信長の追討を受け翌七年脱走し、城は十一月十九日に陥落した。村重は討ち手を逃れ安芸の毛利領まで落ち延びている。
この伊丹城の落武者五名が高野山西光院谷の池之坊という行人寺にかくまわれたのである。
このことを察知した織田方は七月に追捕の使者を差し向け、五人の引き渡しを要求したが、高野山側は「荒木村重の家臣らは山内に居らず」と使者らを追い返してしまった。
さらに翌八月、堺の町奉行松井友閑の兵三十二人が登山して荒木の浪人の行方を探索したが、山内をはなはだしく荒し反感を買った。雑兵の中に元高野山領の百姓であった者三人が案内について来て、老若貴賤を問わず暴力を振るい、土足で堂塔に上がり込んだりした。
憤慨した寺社側では一計を案じ、三十二人の兵を三ヶ所の坊に分宿させて饗応し、熟睡したころを見計らってことごとく討ち果たしてしまったのである。
先年の比叡山焼き討ち、本願寺一向一猤虐殺の情報は既に山門の高僧の間には伝わっていたが、下部にまでは徹底されていなかった。
「なんという恐ろしいことを。信長公の怖さを知らないのか」と憂うる高僧もいた。
高野山は紀伊山脈の東方高山にあって強大な宗門の威力を誇り、一国領主を凌ぐ経済力と権力を保持していた。
故に信長の一連の仏門に対する凶行を知らない僧徒らは、この宗門の権威を嵩に着て、壊に入った窮鳥はこれを保護すべし、と名分をかざし、まさかここまで攻めてくるまい、と比叡山同様信長を見くびり、謀殺に及んだのである。
翌日には早くも三十二人斬殺の報が安土城の信長にもたらされた。信長が激怒したことは言うまでもない。すぐさま下知した。
「諸国を徘徊する高野聖どもを一人残らず搦め捕り、安土へ引っ立てよ」
高野聖とは全国を回って歓進をし、高野参詣をすすめたりする下級僧侶である。
中には宿借を強要して嫌われる者もいた。天正九年八月十七日、信長は捕縛した高野聖六百人を安土城外、京の七条河原、伊勢雲出川原の三ヶ所で処刑した。
この大量殺戮は比叡山、長島一揆と同様信長の残忍性をあらわにしたものであるが、これは兵三十二人を殺された報復と、高野聖が関所通行御免の特権を悪用し、隠密の役を果たしていたためでもある。
引き潮の如く第3話
2020-05-07
引き潮の如く第3話
奈良多聞院の僧英俊は八月十九日の日記に、近日中に出兵がなされるとのことで、来る二十三日には陣触れがあるそうだと記し「高野滅亡時刻来か」と予測している。このころには、高野征伐がはじまる、という噂が世間に流布していたのである。高野聖虐殺の報が入り、ようやく高野全山が危機の到来を悟った。今になって安土へ謝罪の使者を遣わせ、その上、京都仁和寺の任助法親王を通じて朝廷に嘆願した。
勅命が出されたが信長はそれに従わず、高野山包囲の態勢を整えていった。
高野攻めは織田方の軍兵三十二人が斬殺されたことに端を発しているが、これはあくまでも口実に過ぎない。真の狙いは荒野の伝統的で強大な宗教権力と、十数万石といわれていた経済力を潰すことであり、冷徹な合理主義者である信長が、これらを捨て置くはずがなかったのである。
背の山に陣を張ると早速軍議がもたれ、堀秀政、松山庄五郎、岡田重孝、筒井順慶の養子定次ら属将が顔を揃えた。 堀秀政は信長の武将として越前一向一揆、紀州雑賀一揆の鎮圧に功があり、荒木村重の追討にも先鋒の役を果たしていた。が、近ごろは信孝が嫌う羽柴秀吉に接近している。
「秀政は筑前ザルの腰巾着じゃ」と彼は心内で毒づく。
信孝が気に入らなくても軍議は秀政が主導で進んでいった。
筒井定次はまだ経験が浅く、他の武将らはいわば二線級で、信長の天下取りにおいて数々の戦歴を持つ秀政とは格が違う。
軍議によって大手にあたる西方から北方にかけては背の山本陣のほか、紀ノ川筋に沿って二里半(十キロメートル)ほど上流の名古曽付城(砦に相当)に松山庄五郎、下流の粉河付城に堀秀政、名古曽から更に上流の橋本付城に岡田重孝、菖蒲谷に松山信介が陣取った。搦め手にあたる大和口に筒井定次が配置された(末尾略図参照)。この陣容は全て秀政の建議によるものである。
いよいよ高野攻めの布陣が整った。
一方高野方も対決の腹を固め、急遽山内の衆徒や寺領諸荘の地士、領民など五千余を集め、それらの中から器量のあるものを選んで大将株に据えた。
高野山に通じる諸道、いわゆる高野七口のうち北方主要道である大門口、不動坂口、大和口(黒河口)はすでに織田方に塞がれている。高野方は防備の陣として紀ノ川南岸、大門口西国街道の要である麻生津に総大将として南蓮上院弁仙、龍門山雲路砦に大光明院覚乗、寺尾壇砦に医王院政算、九度山の槇野砦に智荘厳院応政、同雨壺山砦に橋口隼人正重藤(副将)、不動坂口の学文路西尾山砦に金光院覚心、大和口地蔵ヶ峯砦に三宝院長敏をそれぞれ配置した。
このほかにも領内の農民を動員していくつかの砦を築き、紀ノ川の南岸を固めた。
戦闘は先ず名古曽の陣の松山庄五郎が学文路から紀ノ川を隔てた北方の平地を攻め、高野方の前衛拠点と目される小田清涼寺などを一気に焼き払った。
清涼寺は弘仁のころ空海が開創したといわれ、小田郷に二十町歩を越える山林田畑を領する、高野山麓随一の有力寺である。周りは豊かな水田に囲まれていた。
このときはまだ高野方では防御の体制が整っておらず、清涼寺には周辺の寺領からかき集められたわずか数十人の雑兵のみが配置されているだけで、本山派遣の僧兵や地士の到着を待っているという状態であった。
そこへ千数百の織田軍松山勢が刈り取られたばかりの稲株を踏み荒らし、攻め込んだものだからたまらない。
指揮官のいない雑兵らでは闘うすべもなく、それでも院主を守りながら逃げ去ってしまった。本堂、庫裡、本尊の薬師如来像等いっさいが灰燼と帰した。「南無大師遍照金綱・・・・」
信心する宗門の寺院が無惨に焼き払われるのを、遠方から目撃した付近の領民らは、恐怖のあまり経を唱えるばかりであった。
続いて菖蒲谷の陣松山信介が子安地蔵寺、妙薬寺などを襲い焼失させた。こうして織田方は高野山への表参道へ通じる要所を抑えたのである。
このように初戦は織田方がまずまずの戦果を上げたのであるが、翌天正十年二月、堀秀政に甲州攻めに加わるよう命が降った。信長は天正三年五月に長篠で武田勝頼を鉄砲戦術により完膚なきまでに打ち破っている。長い柵を設け鉄砲隊を三隊に分け、一隊が撃ったあと弾込めをしている間に次の隊が撃つ、これを繰り前して間断なく射撃するという意表をついた戦術で、怒濤の如く迫り来る武田軍自慢の騎馬隊を難なく仕留めた。
鉄砲隊は足軽で形成されている。その足軽のみで亡き信玄の多くの名将を討ち取ったのである。これほどの戦果はない。
「かような発想がいかにすれば浮かんでくるのか。それがしなどとうていおよばぬこと。感服つかまつった」
明智光秀が信孝に感慨深げに漏らしたことがある。あの光秀が父の天才的な戦術に兜を脱いでいる。信孝の胸中は複雑であった。
この度の甲州攻めは武田家を完全に滅ぼすための出兵である。高野攻めは信長の戦略範囲であるが、軍事上の要地ではなく、比叡山のように緊急的な要素もない。秀政を引き抜いても信孝に任せておけば充分、との信長の判断であった。
「軍師の堀様が引き上げられては作戦に齟齬をきたしまする」
秀政の突然の引き上げ命令に陣営は動揺しかけた。
「総大将の待従様は右府(信長)様の御三男であらせられる。何の憂いが生じようか」
秀政は一同の動揺を鎮めようと懸命であるが、心にもなきことを、と信孝は冷ややかであった。が、このまま黙しているわけにはいかない。
「久太郎の申すとおりじゃ、わしとてこの者に劣らぬほど戦績があるぞ」
信孝は胸を張る。彼も元服したのちは父の天下平定戦に加わり、信忠の陰に隠れて目立たないが、各戦で功も結構立てており、天正五年には従五位下に叙され侍従に任ぜられている。信長は我が子といえども無能で功なき者には、決して官位を与えないのである。
引き潮の如く第4話
2020-05-07
引き潮の如く第4話
「これは大きな心得遣い、申し訳なきことでござった。われら心新たにして待従様の下知に従いまするぞ」
これまで秀政に仕切らせていて影が薄かった感の信孝であったが、その思わぬりりしい姿を目にして岡田重孝、松山庄五郎らの部将は改めて忠誠を表明した。
「かようなときは曖昧な胸の裡を見せてはならぬ。属將どもを飲み込んでしまえ」というのが父に従って闘った経験から得た教訓である。信孝は陣内に起こったわずかの不安を抑え得て安堵したが、引き合いに出された秀政の面白くなさそうな表情を見逃さなかった。
秀政が二千の兵を連れて去っていくのは惜しい気もするが、それでもまだ戦力ではまだ我が軍に有利である。けむたい存在の秀政がいなくなって返って戦いやすいのでは、と信孝は思った。
「大和口筒井勢の坂部と東彎の砦が高野方に奪われました」
秀政が去って十日後の二月十四日、信孝のもとに報が入った。高野勢の反撃が開始されたのである。
比叡山の二の舞を恐れる僧徒らは命懸けであった。浅黄絹の三幅に「金剛峯寺」と大書した軍旗を翻し気勢を上げた。報告によると大和口地蔵ヶ峯高野方の砦の兵が筒井の陣に切り込み、侍大将三好新之允が討ち取られた。敵の砦の副将二見密蔵院と地士西山喜右衛門の槍が凄まじかったという。
「この二人は何者じゃ」
信孝は初めて耳にする敵方僧兵と武者の名に興味を持ち、筒井の使の者に質した。
「双方とも、宝蔵院流槍術の使い手でござります」
「なに、宝蔵院流と申すか」
信孝はこれまでの戦の中で宝蔵院の名を耳にしたことがある。宝蔵院は奈良興福寺の子院である。院主覚禅房胤栄が従来の素槍中心の槍術に対し、十文字鎌を取り入れたのが宝蔵院流槍術である。後に二代目胤舜が戦国末期から江戸時代にかけて繁栄させるのであるが高野山攻防時にはまだそれほど広まってはいなかった。
二見氏は大和宇智郡で畠山氏に属していたが、密蔵院は高野山末寺の僧として頭角を現していた。
西山喜右衛門は高野の地士で紀州伊都郡の大野郷に在している。西山氏は保元の乱で武名高い源為朝の末裔で、喜右衛門はその二十六代目に当たり、近郷では大きな勢力を持っていた。
密蔵院と喜右衛門は宝蔵院の同門で、この度の合戦に喜右衛門は紀ノ川を挟んで織田方本陣真向かいの麻生津に配置されるところを、密蔵院が乞うて大和口に派遣されてきたのである。筒井家名うての豪傑三好新之允と西山喜右衛門は坂部砦の攻防を巡って激しい戦いを展開した。互いの槍の切っ先するどく火花が散る。腕前は互角と見られたが、新之允の素槍に対し喜右衛門の十文字鎌槍の方が有利に働き、最後は鎌槍が素槍を圧倒して新之充が討ち取られたのである。侍大将を失った砦は一気に崩れた。
「宝蔵院流の鎌槍か、いかほどのものでもあるまい」
使の者を帰したあと、信孝は松山庄五郎につぶやいた。長篠の戦い以後戦場では鉄砲が主流になりつつある。まだ白兵戦も主要な位置を占めていたが、一昔前の「やあやあ、我こそは何某」と大将同士が大声で名乗り合うような場面はもう見られなくなっていた。宝蔵院流槍術も強敵には相違いないが、戦いの中の一部であり、信孝は一時的に喜右衛門らに興味を持ったが、以後気にとめることはなかった。しかし、後日その宝蔵院鎌槍に手痛い目を受けるのである。 このときは最も頼れる部隊である筒井勢が崩されたことの方が気がかりであった。
筒井順慶は郡山城主で大和一国を支配していた。順慶はこのとき別の方面に出張っていて、高野攻めには代理として定次を出陣させている。その筒井勢が敗れたのである。
主要戦列の一角を崩されたのは痛手であったが、織田方は信孝の指令により二月晦日の未明、橋本に布陣の岡田重孝の隊が紀ノ川を渡り、学文路口に進出して西尾山の砦を襲った。
学文路口(不動坂口)は京・大阪から高野山を目指す最短距離の表参道で、大門口(町石道)とともに高野七口の最主要道である。
高野山へはどの経路も山脈の二つ三つの小山、中山を越えて本山へたどり着く。奥へ進むにつれて山道は次第に険しくなり鬱蒼とした喬木に覆われる。
高野方の各砦は登り口の小山に構築されている。その一つの西尾山砦は紀ノ川南岸の学文路口へ入ってすぐ、高野山の真下に位置する小高い山に設けられていた。
そこへ織田方二千の軍が襲いかかる。
「うろたえるでない。すぐに各々の配置に着けーっ」
不意を突かれたにもかかわらず高野方守将、金光院覚心の沈着な指揮により千五百の兵はすぐさま迎え撃つ。しばし一進一退が続いたが、岡田隊副将格の二将が討ち取られ織田軍は退却を余儀なくされた。
一方の高野方も多勢の織田軍を撃退したかに見えたが、山門屈指の法師武者である金光院が、敵方の去り際に放った矢を胸に受け討ち死にしてしまった。
学文路口を突破し、一気に本山へ進出しようとした信孝の策は功を奏しなかったのである。
「寺尾壇砦を窺っていた我軍が昨夜不意打ちを受け、崩されましてござります」
信孝の放っている細作から知らせが入ったのは三月四日払暁であった。
渋田の寺尾壇砦は背の山織田軍本陣から紀ノ川を挟んで南東の、やはり小山に設けられていた。この砦は背の山の臣を見張る役目を目的としていた。守将は医王院政算である。さらにこの陣にはかの荒木浪人五人も加わっているとの報がもたらされた。五人は織田方の内情に通じていて、見張りには適していようとの高野方の期待から配置されたものである。
「あやつらはかようなところに潜り込んでおったか。断じて許さぬ。すぐさま五人と捕らえ、ここへ引ったてよ。それにあの目障りな砦もつぶして参れ」
引き潮の如く第5話
2020-05-07
引き潮の如く第5話
信孝の命により本陣の寄せ手の中から五百を選び、三月三日の夕に発ち、山の麓に夜営を張って西尾山と同じように翌未明攻撃を開始する策戦をたてた。
「敵の襲来であるぞう」
その夜は強い雨が降った。夜営の兵団が寝静まったころ、高野方が激しい夜の雨にまぎれて急襲してきたのである。不意を突かれた織田勢は浮き足立ち散々に追い崩された。
織田方の朝駆けの布陣を知った渋田の高野山領民が寺尾壇に知らせたのである。守将の医王院は急遽屈強な法師武者数人をはじめ百人余を選び、夜襲をかけてきたのであった。
「五百の我軍がわずか百に蹴散らされようとは」
信孝は歯ぎしりをする思いであった。父の恐ろしい怒りの表情が目に浮かんだ。
〈高野山の坊主ごときに何を手こずっておるのか、このノロが〉
耳の奥底で罵る声が聞こえたような気がした。
初戦で高野山麓紀ノ川筋の北岸を抑えたまでは戦果があったが、大和口と寺尾では敗北を喫している。高野方は叡山の二の舞を演ずまいと死に物狂いの防戦である。対し信孝自身は仏門の攻撃にはどうも鉾先が鈍っている感がある。背の山に布陣する直前の高野聖虐殺も叡山、一向一揆同様彼の心を痛めていた。
しかし躊躇していてもはじまらない。自身は戦場の真っ只中である。気を取り直した信孝はすぐさま報復の手はずを整えた。
三月十日早暁、侍大将大木権大夫に千の兵を預け、寺尾壇砦を襲撃した。この砦は高野方三百が配置されているだけであったが、万全を期して三倍余の兵を向け、その上信孝が前線では最も信頼する権大夫を起用したのである。
「にっくき僧兵どもを一気に討ち取れ」
権大夫が馬上から檄をとばす。味方が七日前に夜討ちを受け、散々な目に会った恨みがこもっていた。それに充分な兵を与えられ意気も上がっている。
たちまち砦は圧倒的な織田勢に崩されていく。
医王院政算は高野方きっての知将で、総大将南蓮上院弁仙の右腕と目されていたが、その知力を発揮する間もなく数十人もの寄せ手に包囲され、満身に槍を受け絶命した。砦は織田方の手に落ちた。
この戦いの中で荒木村重の五人の浪人は全て討ち死にした。権大夫は生け捕るよう下知していたが、戦いの混乱の中で五人は討ち取られていた。信孝は捕縛することこそできなかったが、父に対する幾分かの申し開きが立ったと思った。
寺尾壇砦の襲撃を成功させた織田勢は、高野方が紀ノ川南岸に配した陣のうち、最も堅固を誇る西国街道麻生津口(高野七口のうち最西端)の飯盛山城を大和筒井勢を除く全軍で総攻撃をかけた。
この城は建武の新政のころ飯盛山山頂(標高七四五メートル)に築かれた山城で、新政権発足時に反乱軍が立て籠もって制圧されたという記録がある。城といっても城主が張り付くようなものではなく、事が生じたときに使用される小城である。
飯盛山城は高野方が、紀ノ川を挟んで北東に本陣を構える織田勢に対する防御の最前線として、強固な陣を配していた。
総攻撃の指揮を執るのは松山庄五郎である。彼は堀秀政が去ったあと副将格となっている。庄五郎よりも岡田重孝のほうが格上であったが、学文路口襲撃の失敗により遠ざけられていた。
城方は高野軍の総大将南蓮上院弁仙、副将で軍師の橋口隼人正、加えて大和口で功のあった二見密蔵院、西山喜右衛門らを配し、総力を挙げた防備態勢で、兵の数も寄せ手には劣らない。
「面妖な。敵方は各砦に散らばっている兵を全て集めても五千のはずである。而るに我が軍と変わらぬではないか」
本陣の信孝は不気味な予感がした。飯盛山攻めに織田方は五千の軍政である。兵の数では高野方を圧倒できると見込んでいた。しかし敵側も対等の陣容である。
高野方は合戦に入ってからも必死で領内に召集をかけ、軍勢を徐々に増やし、今では総勢で織田方に劣らぬ兵力となっている。
四月に入って総力戦が始まった。旧暦の四月はまだ肌寒い。こんな時期の川越である。武者連は川筋から調達(といっても無理に借り上げたもの)した二十艘余りの渡し船での川越であるが、足軽、雑兵らは身ぐるみを頭にくくりつけ、この寒さのなか褌一つで泳いで渡らなければならない。織田軍五千のうち船に乗れる武者はわずか二百ばかりで、ほとんどは足軽、雑兵である。その泳いで渡る様はまるで草食動物の群の大移動である。川岸を上がるとどの兵も全身に鳥肌が立ち、唇が真っ青となっている。
「早う身を整え準備につけい。すぐ出立じゃ、ぐずぐずしていると風邪をひくぞ」
大木権大夫ら侍大将が叱咤する。この寒空の下で泳がされたものであるから口には出さないが、雑兵の中で不満がくすぶっている。
権大夫らが少しでも気を抜くと統制が乱れる。
「山道を駆け登れば、たちまちからだが暖まろうぞ」
飯盛山頂まではところどころ急坂がある。権大夫らに尻をたたかれ素早く隊列を整えた織田軍は、二列縦隊で山道を行軍する。
山頂に城が見える地点まで来たとき、松山庄五郎が一団をいっとき停め、物見からの報告を待つ。
「敵はわれらが近づいたことを、察知してはおりませぬ」
庄五郎はさっそく権大夫を呼び、進撃の下知を降した。
「われら必ず敵の大将弁仙の首級を取り、徒従様へのご恩に報いたいと存じまする」
大木家は代々織田家に仕えている。父の代まで足軽大将の身分であったが、権大夫の武勇ぶりに目をつけた信孝の推挙により侍大将に取り立てられたのである。
権大夫はほか三騎の侍大将はじめ騎馬武者、徒武者に引き連れられた五千の軍団は飯盛城を目がけ、鬨の声を張り上げ城に向かって突き進む。
山頂当たりは急峻な坂である。寄せ手が城にたどり着こうとしたとき不意に城方から討って出てきた。
城方は待ち伏せをしていて、物見は欺かれたのである。
引き潮の如く第6話
2020-05-07
引き潮の如く第6話
「おのれ猪口才な、目にものみせてくれるわ」
権大夫が馬上で槍を構え先頭きって突進していく。
騎馬武者、徒武者、足軽、雑兵入り乱れての殺し合いがはじまる。山の上手から押し寄せる城方の雑兵が腰を引いたまま槍を突きつけてくる。にわかにかき集められた戦経験のない軍団であることが、戦いに明け暮れてきた寄せ手には一目でわかる。上手の方が有利なはずであるのに互角になっている。寄せ手の先鋒が槍を突っ込む。城方からも勇猛な兵団が繰り出し双方が血みどろとなる。
狭い山道のことゆえ転がっている屍を踏み越えて槍を突き合わさなければならない。
拮抗した攻めぎあいで膠着状態が続いたあと、城方の後方から二見密蔵院と西山喜右衛門率いる鎌槍隊五十人が前方に出て攻撃に入った。
織田方の兵らは初めて目にする十文字長槍に不気味さを感じた。
「かかれーっ」
敵方がたじろいだ一瞬を見逃さず喜右衛門が号令をかけると鎌槍隊が突き進んだ。織田勢も素槍を構えて応戦するが鎌槍の敵ではない。
鎌槍は素槍よりも一寸(約三十センチメートル)ばかり長い。それに穂先が十字型になっているので、素槍が突いても跳ね返されてしまう。上手からわずか五十の鎌槍隊に織田軍は見る見るうちに圧倒され次第に後退していく。 戦場では刀以上に鎌槍が重視されていた。甲胄に身を固めているので、刀で切りつけても刃は届かず切っ先で突き刺さなければ致命傷とならない。突き合いであれば柄の長い槍の方が有利に決まっている。その従来の槍が更に長い鎌槍に翻弄されている。
「ものども、退がるな、えーい、退がるでない」
馬上から権大夫が大声を張り上げる。それでも退勢を盛り返すにはほど遠い。ふと敵陣で指揮を執る屈強な武者の姿が権大夫の目に入った。
「こやつが西山喜右衛門であるな。大和口に続いてこたびも我が軍を苦しめおって。こしゃくな奴め」
権大夫が憤怒の形相で馬を操り、喜右衛門目がけて長槍を構え襲いかかっていった。
それを鎌槍隊が素早く阻もうと一斉に立ちはだかる。
「えーい、じゃまだていたすな、雑兵どもが」
二本の鎌槍が同時に権大夫を襲う。その鋭い切っ先の一本を手槍ではね除けたが、二本目が権大夫の槍を摺り込んだまま鎧の胸を突き通した。素槍ではこのような芸当はできない。鎌槍の恐るべき力である。
堪らず権大夫は落馬した。すかさずとどめの槍が襲う。
「無念じゃー。侍徒さま、申し訳ござりませぬ」
権大夫は喜右衛門と一戦を交えることができぬま鎌槍隊に討ち取られた。
勢いを得た城方は上手から怒濤の如く押し寄せ、織田方はたちまち苦戦を強いられる。権大夫に続いて三人の侍大将が討ち取られ、ついに総崩れとなった。
「退けー、退けー」
庄五郎が退却の下知を飛ばす。城方はなおも追い討ちをかける。山道のいたるところに屍体が転がっている。その中には身体に突き刺さった槍を握りしめながら、無念の形相で息絶えている織田方武者の骸もあった。さらに紀ノ川にも無数の屍体が浮かんだ。
「侍従様の御名を汚し、まことに、申し訳ござりませぬ」
背の山本陣で命からがら逃げ帰った松山庄五郎が飯盛山敗戦を報告したあと、土下座し涙ながらに許しを乞うている。
「もうよい、そちばかりの責任ではない。それよりも権大夫はさぞ無念であったろう。まことに惜しい武者を失うた」
「ははーっ、もったいなきお言葉。当人もさぞ浮かばれることでありましょう」
このとき既に信孝は覚悟を決めていた。だから武勇を振るうことがかなわぬまま、討ち死にした権大夫を思いやることができたのである。
父信長は背いた者、意に添わなかった者に対して厳しいことは無論、功なき者や目立った働きのない者も仕置きした。 先年、譜代の宿老である佐久間信盛、林通勝らを後者の理由で追放している。まさか我が子にまでは、という思いもあるが、あの父には計り知れない不気味なところがある。
いま、飯盛山で味方が総崩れの報を耳にし、一瞬父への恐怖感が信孝の胸中によぎったが、すぐに腹が据わった。 どんな仕置きでも受けよう。だがその前にやっておきたいことがある。それは合戦が始まって以来、気になっていたことであるが、敵方の兵力が日を追って増えてきていることである。
最初は攻撃側の方が優位であったが、今では逆転されている。このままでは不本意な戦いを強いられることになりかねない。
これまでの父や二人の兄の戦い方は、信孝の知り得る限りでは圧倒的な兵力の差で勝利をおさめている。 信雄などは勝手に伊賀攻めを試みて敗退し、父から厳しい叱責を受けたが、高野攻めがはじまった昨年九月、正式に信長からの伊賀の征伐を命ぜられた。四万の大軍と惟住五郎左衛門(丹羽長秀)、織田信包、筒井順慶などの一線級の武将が付けられたのである。
これに対し伊賀勢は五千人余で、いくら忍びの術に長けた者揃いといえども敵うすべもなく、八日間で伊賀は平定された。
「これほどの戦力差であれば、いかようにも戦えるわ」
信孝は悔しかった。伊賀攻めは四万でこちら八千である。どう見ても納得できかねる。
「援軍を要請してみよう。叶わなければそれまでだ」
と信孝は腹を決めた。これが予期せぬ結果をもたらしたのである。
信孝の援軍要請に対する父の返書が届いた。
冒頭は予期したとおりの厳しい叱責であったが、そのあとには思いもよらぬ内容が記されていた。
「高野攻めには摂律に配している惟住の軍のうち五千を遣わす。それには百挺の鉄砲隊も加えてある。そなたには四国の長宗我部征伐を命じ、平定後は讃岐一国を与える心づもりなる故、一気に決着をつけて戻って参れ」
引き潮の如く第7話
2020-05-07
引き潮の如く第7話
信孝は何度もこの項を読み返した。初めは信じられなかった。
「父は自分を疎んじてはおらせられなかったのだ」
信孝は感涙にむせんだ。父への恐怖感もわだかまりも一挙に吹き飛んだ。
信孝はこれまで母親の身分が低いため、長男、二男とは大きく差をつけられてきた。彼は常々不満を抱いていたが、この時代当然の慣わしともいえるのである。
正室に嫡子ができれば妾腹の子は他家や家臣の養子に出されたり、捨て扶持程度(つまり冷や飯食い)の待遇しか与えられなかった。
事実信長の四男以下はこのような待遇である。しかし信孝は妾腹にもかかわらず、禄高こそ五万石ではあるが、大名であり信長軍団の有力な武将としての待遇を受けてきている。
このことは父信長が早くから三男の資質を見込んでいたからに他ならない。本人が気付いていなかっただけである。
書状の中に一つだけ気がかりなことが記されていた。それは四国攻めの副将に惟住長秀を任ずるとあったことである。副将は当然惟任光秀であると信孝は思い込んでいた。
光秀はこれまで長宗我部との交渉に当たってきた。四国攻めには彼が副将として最も適しているはずであるし当人も自任しているであろう。戦績からみても長秀には差をつけている。
信孝は、いつか惟任とともに戦いたい、というのが幼少からの念願である。しかし、あの父に対し、惟任を副将に、とはとても進言できない。
「父上と惟任の間にいったい何があったのか」
何かがあったとすれば惟任が危ない。父は己に一物を持つものは絶対に許さない。いくつもの前例を見てきている。が、わかっていても今の非力な自分では惟任に何の力にもなってやれない。今は五千の援軍到着を待ち、高野勢を打ち破るしかない、と信孝は胸に言い聞かせた。
五千の兵もさることながら百艇の鉄砲隊は何よりもありがたかった。
「よーし、鉄砲隊が来れば鎌槍なんぞ物の数でない。これで高野の坊主どもを一気に全滅させてやるぞ」
そのころ、京では信孝の想像もつかぬ事変が起こらんとしていた。
「惟任日向殿が本能寺を攻め、右府様は自刃なされました」
援軍到着の前日である天正十年六月二日の昼下がり、京から早馬の変報が届いた。
げーっ、と信孝はその場にうずくまり激しく嘔吐した。顔面は蒼白となっている。
〈大将たるもの、いかなる場においても、取り乱してはなりませぬぞ〉
皮肉にも父を殺した光秀の声が聞こえたような気がした。
信孝はすぐ起ち上がり、異変の全てを話すよう促した。
「大事ありませぬか」
使いの者は信孝を案じたがかまわず続けさせる。
兄信忠も二条城に立てこもったが、大軍に攻められ自刃したという。
一部始終を聞き終えた信孝は注意深く周囲を見回した。既に人払いをしてあったのでこの場は使いの男と二人だけである。
「ちと大事な用がある。こちらへ付いて参れ」
信孝は男を本陣裏手の雑木林まで連れて行く。林には鬱蒼とした木々が生い繁っていた。
「もそっと近う」
何の疑いもなく男が近づいてくると、信孝は素早く脇差しを抜きその胸を刺した。男は目を剥いて一瞬信孝を見遣ったが、声を出すこともなく仰向けに倒れていった。
父の死を誰にも覚られてはならぬ、と信孝の咄嗟の判断であった。男への哀れさも感じたがすぐに消えた。屍を林に捨て置き足早にその場を去った。
「惟任が、なにゆえ父上を・・・」
我に返ると信孝の胸に沈痛な思いが襲ってきた。
父は長宗我部討伐の後、讃岐を与えると約束してくれた。我を武将として初めて認めてくれたのである。思いもよらぬことであった。
「なぜ自分に」と長く胸につかえていた高野攻めの命令も、信雄よりも信を置いていたからこそ我に降したのではないか、とさえ思うようになったばかりである。
幼少のころから鬼のように恐れていた父を、やっと理解できるようになってきたと思っていた矢先の変事である。
なぜ、惟任が、という思いが何度も胸をよぎる。
信孝には思い当たることは何もなかった。彼が知り得ている範囲では、光秀は信長にとって最も有能な重臣で、彼の働きにより摂津と紀伊を除く畿内を制圧していた。畿内は天下統一には最も重要な位置である。その攻略を任すということは信頼関係が相当厚かったに相違ない。光秀は信長の信頼にこたえていた。信孝から見れば光秀は信長に臣従しており、謀反を起こすような人物とはとても思えなかった。
ただ一つ腑に落ちないのは、光秀が四国攻めから外されていることである。父との間に何かがあったに違いない。それは何か、いくら考えても思いの至らぬことであった。
信孝が高野攻めの命を受けた天正九年ごろ、光秀はまだ信長の信任を得ていた。
この年の二月信長は京都で馬揃えをおこなっている。馬揃えとは観兵式のようなもので、式場(馬場)を御所の東側にもうけ、名馬を取り揃え麾下の軍勢で編成し騎馬隊を行進させ、天皇に見せるのである。織田軍団の威容を天下に示すためでもある。 光秀はこの馬揃えの奉行を勤めた。
馬揃えは信長の思惑どおり朝廷の公卿衆への示威となり、多くの観衆にも事実上の天下人であることを示した。
「そち以外に奉行の役を果たせる者はおらぬぞ。」
式を終え信長は上機嫌で、見事馬揃えの采配を振るった光秀を褒めた。
光秀が信長から信を得ていたのはこのときあたりまでであった。
引き潮の如く第8話
2020-05-07
引き潮の如く第8話
信長は京へ入り天下平定の野望が着々と進んでいくうち、次第に傲慢さが芽生えてきた。家臣には生きた神としてあがめさせ、恐怖的な支配を敷きつつあった。
「上様はお変わりになられた」
光秀は近ごろ内心でよくつぶやくようになった。
足利義昭を将軍の座から追い落としたあと、家臣や諸大名は信長を、上様と呼ぶようになっていた。
その義昭を将軍に仕立て上げたころ、光秀は将軍家と織田家に仕えていた。彼は故実、典礼に通じ朝廷や将軍家との仲立役として、信長から重用されていく。
尾張の小大名時代から仕える織田家譜代の家臣団には光秀のような人物は存在しなかったし、さらに戦場においても数々の功績をあげていったので、信長はとりわけ彼を気に入り、やがて譜代の重臣柴田勝家、佐久間信盛と肩を並べるほどになっていく。
佐久間信盛を追放した際の信長自筆の折檻状には〈丹波国での光秀の働きは天下の面目を施した〉と記されている。
「諸国を浪々としていた身が、上様のおかげでこれほどまでになろうとは」と光秀が感謝の念を抱いていたのは当然といえよう。
しかし馬揃え奉行の大役を果たしたあと、信長の自分に対する態度が、どうも冷たい。
つい先日も安土城へ勅使が高野助命の勅命を携えて下向した折、信長は常着で迎えようとしていた。彼はこの勅命を承るのみで従う意思は毛頭ない。しかも我が居城で迎えるのであるから常着で充分、という考えであった。これを知った光秀は迷った末、意を決して進言した。
「勅使をお迎えするに、常着ではあまりにご無礼かと存じますれば、ぜひ大紋直垂をお召しあそばせ」
「そのような着衣は肩が凝っていかぬ、常着でよい」
信長は不機嫌そうに一蹴した。光秀はなおも食い下がる。主君を思えばこその進言である。
「この痴れ者が出過ぎし口をききおって。もうよい、即刻坂本へ立ち帰れ」
信長のすさまじい怒声に光秀は畳に額をすりつけるほど平伏し、座敷を退出した。
他の家臣に対する罵声は幾度も目にし、耳にしてきたが、自身に浴びせられたのは初めてのことであった。
光秀は信長のあの目のつり上がった怒りの表情に狂気を見てとった。
「上様は何故あのように・・・」
以前は礼式、装束など全て彼の具申を採用してくれた。なぜか、光秀の胸中は暗雲が広がっていく思いであった。畿内を平定し織田氏政権の基盤がゆるぎなきものとなり、もう自分の役目は終わったのであろうか、と光秀は思いはじめた。
そこへ近ごろ羽柴秀吉の中国攻めの働きが家中で注視されてきた。信長は秀吉からの報告の使者が来ると機嫌良く接見した。
光秀は秀吉との出世競争では常に先んじてきた。
彼が坂本城主となった二年後に秀吉が長浜城主となっているような具合である。それが秀吉の中国毛利攻めの著しい戦功により、追いつかれすでに追い越された形勢にある。
天正十年五月信孝に高野攻め援軍派遣と四国攻めを命じる書面が届いたころ、光秀に中国へ出陣命令が降った。そのときすでに四国攻めの副将は惟任長秀と決まっていた。
光秀は当然信孝の後見として四国攻めを任されるつもりでいた。それに彼はこの戦いで信孝を信忠、信雄に劣らぬ武将に育て上げたかった。そこへ中国出陣という追い打ちである。形の上では総大将の信長に従うことになるが、中国戦略は秀吉が主将であり、光秀は事実上彼の組下となる。
「どうやらわしは見捨てられたようであるな」
光秀はここへきて初めて自身の立場を悟った。彼は信長の変化に気づくのが遅すぎたのである。
信長は入京以来光秀の学識と朝廷や公家に対する巧みな外交手腕を高く評価してきた。しかしほぼ天下を掌握し、確固とした地位を築いたいま、彼を必要としなくなってきていた。それどころか近ごろではその学識ぶりがうとましく思うようになっていたのである。
尾張の小大名時代に今川義元という大敵を打ち破り、群雄が割拠する乱世を、その並はずれた戦略で制してきた主君に畏敬の念を抱いてきたが、学識では負けないと密かに光秀は自負してきた。しかしその心うちを信長にすでに見破られていた。
光秀は信長に恐怖心を抱きながらも亀山城で中国出陣に備えて一万三千余りの軍勢を召集していた。
そこへ、信長が百に満たない供回りで上洛し、四条西洞院の本能寺に宿泊し、信忠も二千の兵を率い二条明覚寺宿陣しているとの情報が入った。
「このわしをそそのかしておるのか」
光秀は、この報に接した当初はむしろとまどい気味であった。が、だんだんと謀反の心が芽生えてきた。
〈このままでは、わしは滅ぼされるか、一生秀吉の組下におかされるかだ。秀吉はちかごろ信長のご機嫌取りにきゅうきゅうとしている。それを受け入れている信長もそれまでの人物だ。こんな男につぶされるのであれば、いっそのこと・・・〉
急に天下取りの野望が沸いてきた。
確かに信長は乱世においては図抜けた戦略を持ち実践してきた。自分にはとうてい及ばないと光秀も認めている。しかし治世には不向きである。すでに専制、圧制のきざしが見えている。天下平定後の行政手腕は自分の方が優れているとの自信を持っていた。
光秀は、ここで天が与えてくれた二度とない好機を逃すまいと決意した。
秀吉は中国、勝家は北陸、他の主立った武将も各地の前線で戦っている。信長は裸同然で謀反企ての邪魔をする者は誰もいない。ただ一つ気がかりなのは信孝のことであったが、それも幸いなことに紀州高野攻めに出陣中である。
光秀は足利義昭に仕える以前は越前の朝倉家に仕えていた。その前は仕官を求めて諸国をさすらっていた。野宿し食うや食わずの日々を送っていたこともあった。
織田家に仕えてから三男信孝が優れた器量を持ち合わせながら、同年の兄信雄に差をつけられ悔しい思いを抱いていることを知り、この立場の弱い三男を励まし続けてきた。彼も父以上に自分を慕ってくれた。どこか相通じているところがあるような気がした。
その信孝は遠方の紀州にあり、他の有力武将と同様に釘付け状態にあるからひとまず安心である。
六月一日未明、亀山城を発した明智勢一万五千は、桂川を経て本能寺へと進軍していった。
引き潮の如く第9話(最終話)
2020-05-07
引き潮の如く第9話(最終話)
信孝の行動は素早かった。父信長の死を極秘のまま退却の下知を発した。父の死を味方に知られると全軍に動揺が走り、逃亡する者が続出するであろう。また敵方に漏れると勢いを得て攻められ、一軍は全滅する恐れがある。援軍を待っていても間に合わない。否、その援軍も異変を知って引き上げているかも知れない。
「父上から早急に引き上げよとのお達しである。我らは直ちに堺へ向かい、惟住軍と合流する」
訝る部将らには強引に押し通した。
このまま引き上げるのは信孝にとっても断腸の思いである。初めのうちこそ鉾先が鈍っていたが、味方が苦戦する中で次第に変わってきた。大木権大夫が討たれたころになると完全に高野勢に対し憎しみを持つようになっていた。そして援軍が到着次第総攻撃を開始し、一気に攻め滅ぼす腹づもりであった。
しかしもう高野攻めは終わった。
信孝は素早く気持ちを切り替えた。いくら心を通わせていた光秀といえども父の仇である。対決を避けるわけにはいかない。
父も、その後継者である兄も今は居ない。次兄の信雄と後継者争いとなることは必定である。
「我に父上の後を継ぐ器量はあろうか」との不安もいっぱいであるが、今は一時も早くこの場を立ち去ることが肝要である。
織田軍数千の兵は潮が引く如く去っていった。
今回で、「引き潮のごとく」の連載は最終回を向かえました。愛読ありがというございました。